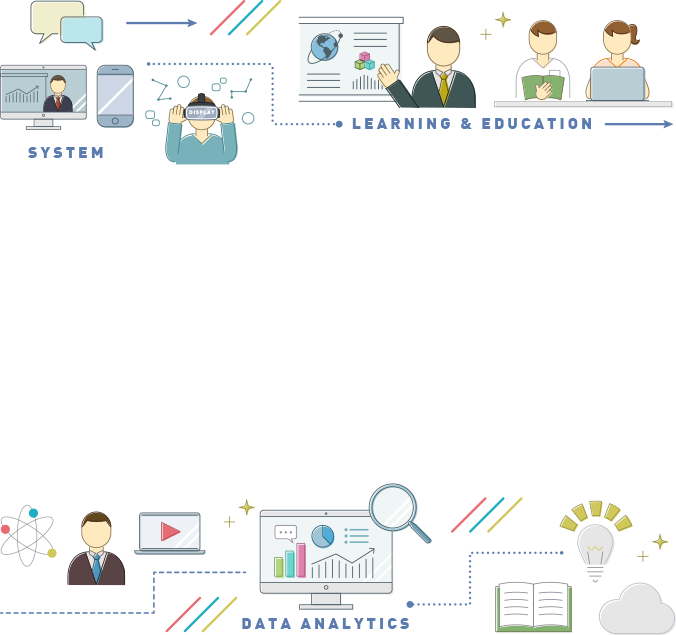

-
LLMを活用する方が読解の個別支援に効果的か?――LECTORの提案論文を読んで
2025年08月18日
皆さん、こんにちは。李です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文について、その内容と私の感想を交えて紹介したいと思います。 論文タイトル:LECTOR: Summarizing E-book Reading Content […]
英語文献ゼミ
-
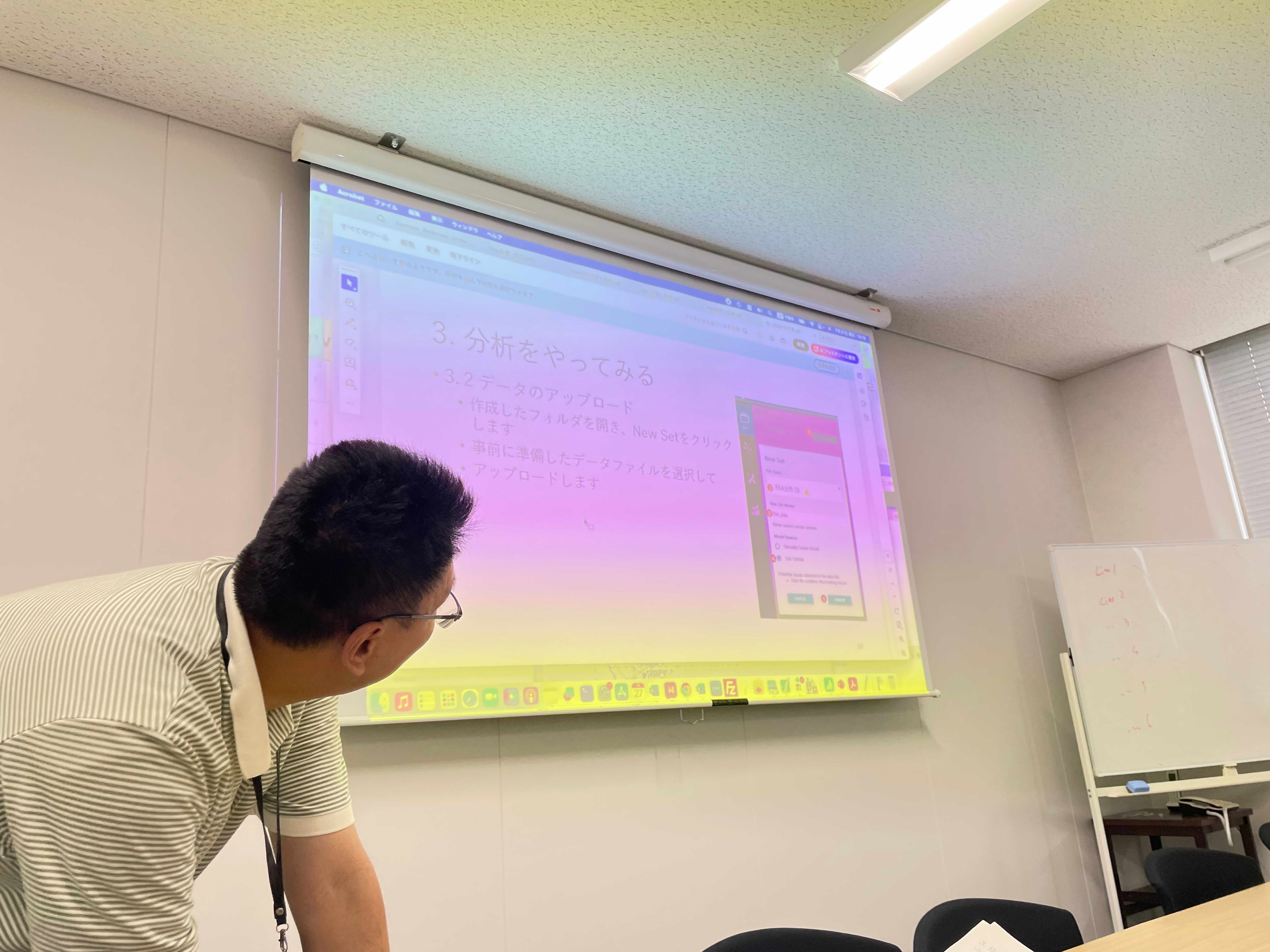
2025年08月11日
毎年恒例になりつつある、研究・分析手法を学ぶ集中ゼミですが、今回はENA(Epismetic Network Analysis)を扱うこととなりました。質的なデータをコーディングなどの処理を行い、定量的に扱うことができる […]
報告
-
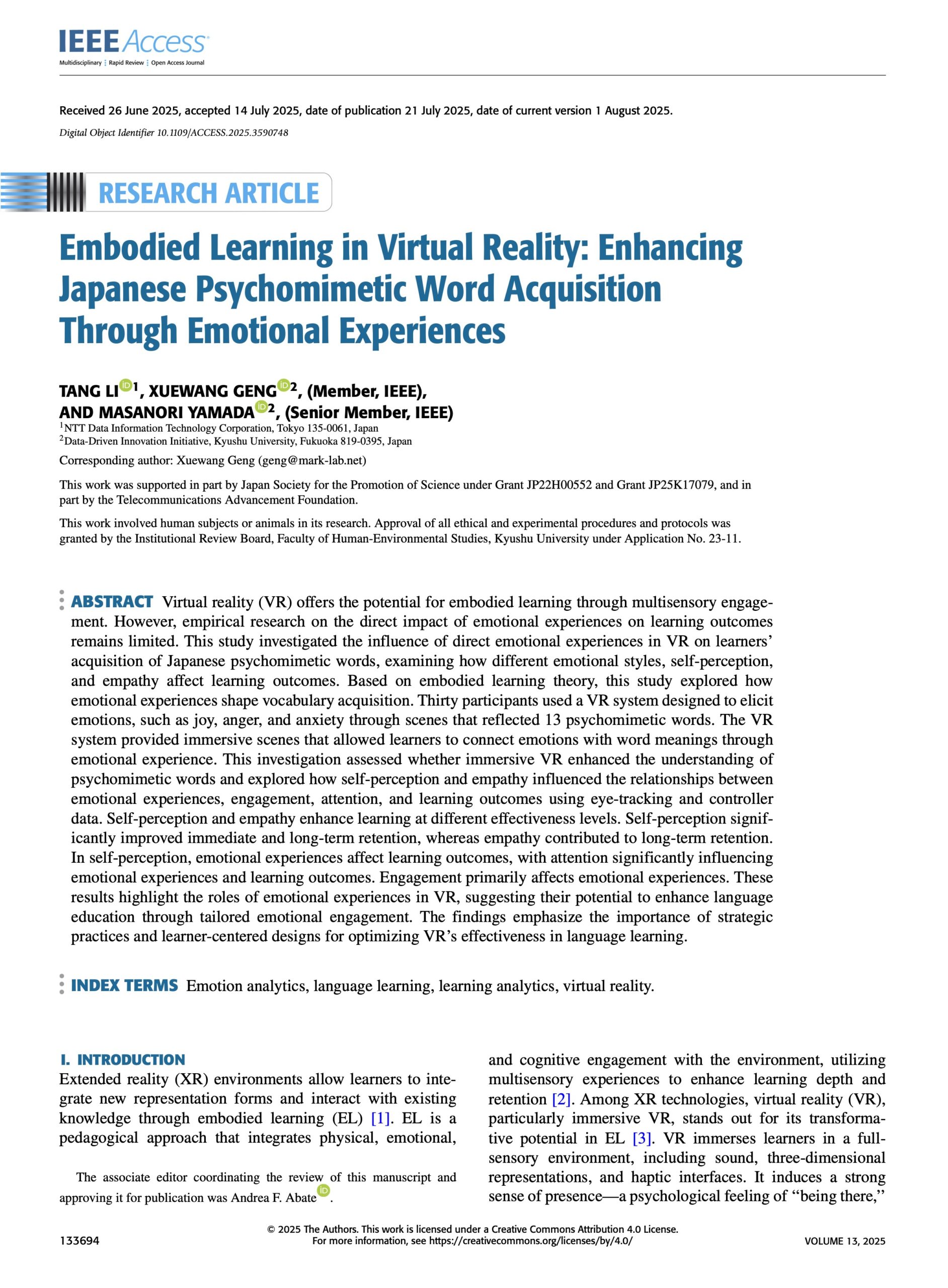
2025年08月04日
結構、時間がかかりましたが、山田研修了の李さんが修士の時にやっていた、感情に関わる日本語オノマトペ学習を支援するVRシステムの開発・評価の内容がIEEE Access誌(Impact factor 3.6, Google […]
報告
-
教師のデータ活用力を高めるには?研修プログラムの成果とLADデザインへの示唆
2025年07月28日
皆さん、こんにちは。修士2年の樋口です。 去年の9月からトルコへ交換留学に行っていたのですが、6月に戻ってまいりましたので、これからまた山田研究室で研究を頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 この記事では、 […]
英語文献ゼミ
-
2025年07月22日
皆さん、こんにちは。研究生の李です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文について、その内容と私の感想を交えて紹介したいと思います。 論文タイトル:A Chain-of-Thought Prompting Approach w […]
英語文献ゼミ
-
ChatGPTによる英語ライティングの採点精度は?―教師の採点との比較
2025年07月14日
みなさん、こんにちは。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介します。 論文タイトル: Exploring ChatGPT as a writing assessment tool ジャーナル: Innovations i […]
英語文献ゼミ
-
2025年07月07日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル:Does Gamification Influence Students’ Online Le […]
英語文献ゼミ
-

ラーニングイノベーショングランプリにて最優秀賞を頂くことになりました!!
2025年07月02日
大変光栄なことに、ラーニングイノベーショングランプリにて、福嶋政期先生、そのお弟子さんの修士2年 相浦航くん、山田の共同研究チームで応募しておりました、保育VRシステムに対して、最優秀賞を頂くこととなりました。まずは審査 […]
お知らせ
-
小学校における自己調整学習方略を促進する教師向けダッシュボードのデザイン
2025年06月30日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル: Designing a classroom-level teacher dashboard to fost […]
英語文献ゼミ
-
LLMに思考能力を持たせるには、そしてそれを教育工学にいかに応用できるか?
2025年06月23日
皆さん、こんにちは。研究生の李です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文について、その内容と私の感想を交えて紹介したいと思います。 論文タイトル:Chain-of-Thought Prompting Elicits Reas […]
英語文献ゼミ
-
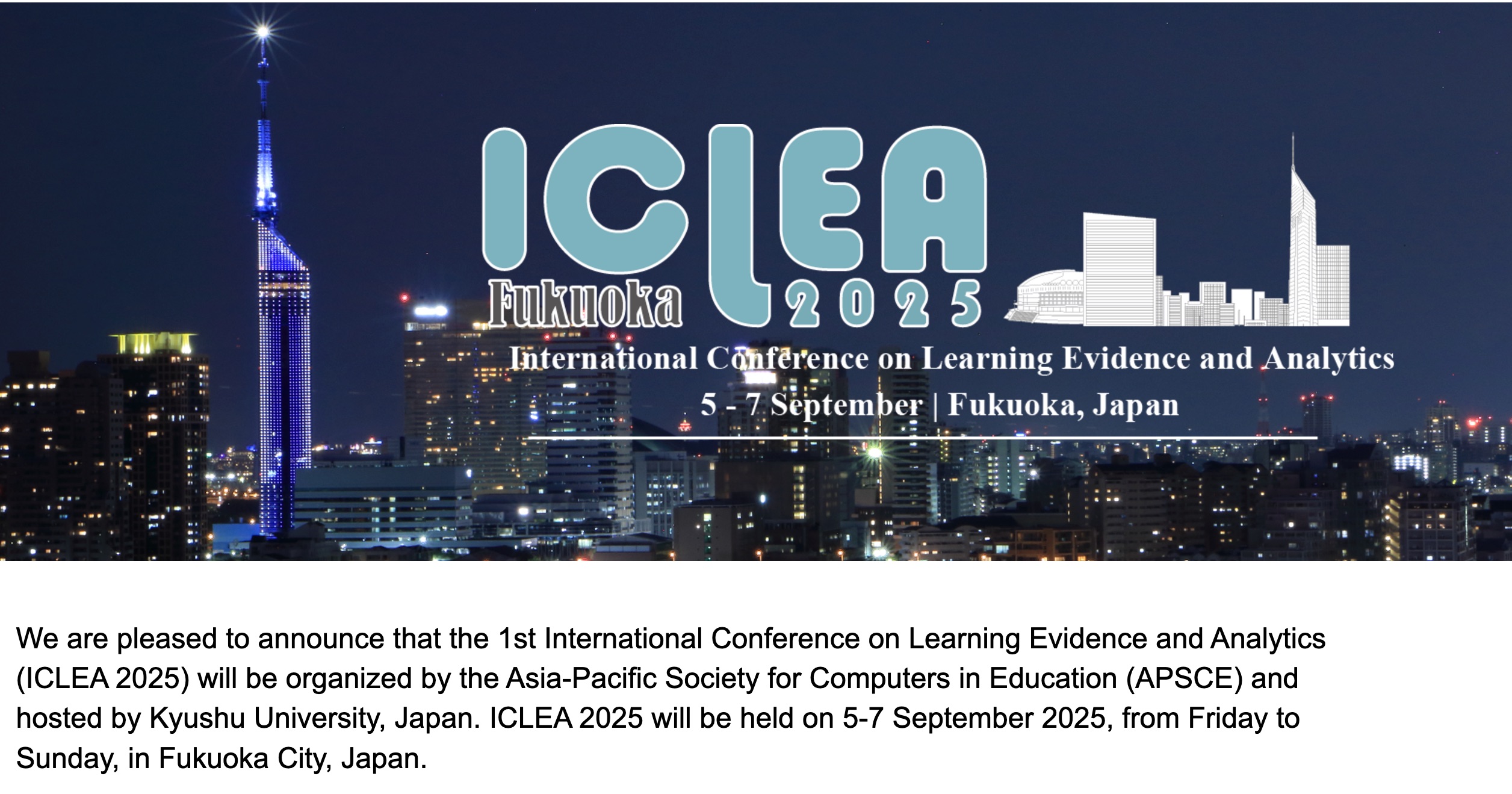
2025年06月18日
今月は2つの国際会議の採択結果が来ました! 1つは、ICCEのSIGが運営している国際会議”ICLEA 2025″にて、山田研から3件投稿していましたが、3件とも採録されました。査読してくださりま […]
報告
-
高校生は英語ライティング学習にAIツールをどのように活用しているのか?
2025年06月16日
みなさん、こんにちは。田中です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介いたします。 論文タイトル: English as a foreign language (EFL) secondary school student […]
英語文献ゼミ
-
児童生徒はゲーム中にどのようなプロセスで問題解決に挑んでいるのか?
2025年06月09日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル:Uncovering students’ problem-solving processes in game […]
英語文献ゼミ
-

2025年06月02日
いやー、耿先生、がんばりました。本当におめでとうございます!また本件、査読してくださった先生方にも感謝いたします。有意義なコメントを頂き、内容としても、とても充実したよい論文になりました。 時間かかりましたが、無事、SA […]
報告
-
2025年05月26日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル: Leveraging Process-Action Epistemic Network Analysis […]
英語文献ゼミ
-

2025年05月19日
とうとう眼鏡をかけることにしました。視力は1.0、1.2はあるのですが、ディスプレイに映った字がブレて、とても読みにくく、ワープロソフトを1.5倍くらいに拡大しないとはっきりと読めなくなったのです。車の運転中や外の風景と […]
雑談
-
2025年05月13日
みなさん、こんにちは。博士後期課程1年の田中です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介いたします。 論文タイトル: Large language models fall short in classifying lea […]
英語文献ゼミ
-
ゲームベースの学習で、どのように内省を支援すれば効果が最大化されるのか?
2025年05月07日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル:Game-based learning analytics for supporting adolescen […]
英語文献ゼミ
-
潜在クラス分析を活用した協調学習におけるマルチモーダル学習パターンの解明
2025年04月28日
皆さん、こんにちは。 この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。 論文タイトル: From Complexity to Parsimony: Integrating Latent Clas […]
英語文献ゼミ
-
EFLライティング指導へのLLM統合: ライティングスコア・自己調整学習方略・モチベーションへの影響とは?
2025年04月21日
EFLライティング指導へのLLM統合: ライティングスコア・自己調整学習方略・モチベーションへの影響とは? みなさん、こんにちは。博士後期課程1年の田中です。 先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介します。 論文タイトル: […]
英語文献ゼミ
教育工学の研究をしたい方へ
私は研究室に所属する学生には、どの進路に進むにしろ、積極的に、活発的に、将来の専門家として、
そのポテンシャルが発揮できるように育って欲しいと願っています。
そのためにも、自分で国内外の様々なリソースを探し、学習機会を積極的に見つけ、成長していって欲しいと思います。
修士もそうですが、企業・官庁自治体などに行っても、また博士課程に進学しても、なんでも0から教えてもらえるということはまずないです
(社会人学生なら身にしみて、理解されていると思います)。
何がわかっていて、何がわかっていないのか、それがわかるためにはどうすればいいのか、
どういう方法で学習(仕事)することが自分に向いているのか、
専門的にいうと、メタ認知を発揮をして、行動に移すことが求められます。
これは私の学部での授業方針もそうですし、修士であればなおのこと、意識してやっています。
そういうことをみんなで学んで、お互いに助け合い、成長していける研究室にしたいと願っています。
山田研究室では修士課程・博士課程入学希望者を募集しています。
日本、世界の教育の発展に寄与したい方、来たれ!


山田 政寛(やまだ まさのり)
