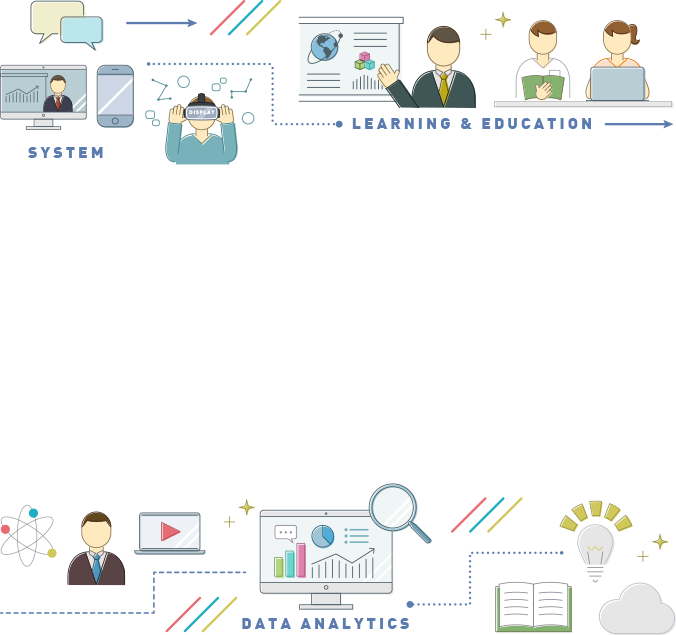皆さん、こんにちは。
この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。
論文タイトル:Game-based learning analytics for supporting adolescents’ reflection.
ジャーナル:Journal of learning analytics,
出版年:2021
巻号:8(2).
著者名: Cloude, E., Carpenter, D., Dever, D., Azevedo, R., & Lester, J.
この研究は、ゲーム型学習 Crystal Island を舞台に、学習者が行う「内省(reflection)」の量と質が知識獲得と問題解決に及ぼす影響を検証したものです。
背景として,21 世紀型スキルを育む PBL や GBLE(Game Based Learning Environments)が普及する一方、ゲーム内に体系的な内省支援が欠けているために学習効果が不安定であることが指摘されています。内省は経験を批判的に見直し意味づける過程であり、アメリカの教育課程には明示的指導が少ないため、多くの学習者が十分な問題解決スキルを身に付けられていないと報告されています。
1.理論的枠組み
この研究では McAlpine ら(1999)モデルを採用し、内省を以下の 4 段階で可視化しました。
①意識(目標と現状を自覚する)②説明(経験を言語化する)③関連づけ(過去の知識や経験と結び付ける)④統合(得た知見を将来の行動に反映する)の4つです。
この枠組みにより、内省の深さを「学習目標との整合性」という観点で定量化できる点がポイントとなっています。
2.方法
アメリカの公立中学校の 120 名を無作為に抽出し、微生物学を題材とした謎解き GBLE であるCrystal Islandをプレイしてもらいました。学習目標は「微生物学概念の理解」と「病因の特定・解決策提示」の二つです。
内省プロンプトとして、ゲーム内の重要アクション直後に(1)学んだ重要情報は何ですか?(2)現在、解決のためのアプローチとして考えているものは何ですか?(3)別のアプローチで解決するにはどうしたら良いですか?の三種類が、ゲーム上で重要な行動をした後に提示されました。
内省の量は記述回数、質は「観察・熟考・検討・仮説形成」の 4 要素に基づき評価しました。学習成果に関する指標は事前後の知識テスト得点とゲーム中の問題解決成功数(病因特定・解決策提示の正否)です。行動ログも収集し,多面的に分析しています。
3.結果
参加者が記述した内省の量・質と、知識テストの得点変化及び問題解決の成功数(ゲーム中)との相関を分析しました。
結果として、内省の量と知識テスト得点の変化には有意な正の相関が認められましたが、問題解決成功率との関連は見られませんでした。一方で、内省の質が高いほど、知識得点・問題解決ともに成績が向上しました。特に仮説形成を伴う記述が最も強い予測因子でした。プロンプト別の分析では「代替案を考える」問いが最も深い内省を誘発し、学習成果への正の影響も最大になりました。
4.考察
この研究の結果より、以下の点が示唆されています。
(1)内省に関しては量より質が問題解決への効果として大事な要素である点
内省回数を増やすだけでは十分でなく、目標に直結した戦略的熟考・仮説形成が伴わなければ問題解決力は伸びないと示されました。
(2)問い(プロンプト)のデザインが鍵となる点
代替案に関するプロンプトが深い熟考を促した結果から、「いつ・何を問うか」という設計が内省の深さと成果を左右することが分かります。
(3)ラーニングアナリティクスによる可視化と個別化について
行動ログや発話・視線データを統合するマルチモーダルラーニングアナリティクスを用いることで、内省支援をリアルタイムかつパーソナライズできる可能性があります。
実際にこの研究結果を授業デザインへ適用する場合について、教師は学習者が目標に向かい行動できるよう、内省を支援する活動や問いかけを意図的に組み込むことが求められます。また内省の支援は単に認知的活動として捉えず、メタ認知や自己調整学習との連携の中で設計されるべきであり、ゲーム環境のようなインタラクティブな場面において、内省がどのように行動と結びついているかを捉えることで、より効果的な支援が可能になるということも指摘されています。
限界と今後の課題として、以下の点が指摘されています。第一に、内省の質の評価は記述文に基づいて行われており、学習者の実際の思考過程を完全に反映しているとは限らない点です。これについて、発話や視線追跡、行動ログなどを組み合わせたマルチモーダルな分析が今後求められます。
第二に、この研究では内省のタイミングがゲーム内の特定のイベントに基づいて自動的に提示されていましたが、学習者自身のタイミングで内省を行う自由記述形式や、自己選択的なプロンプトの有効性についても検討する必要があります。
第三に、学習者の個人差(例えばメタ認知能力、動機づけ、学習形態等)を踏まえた内省支援の個別化も、今後の研究課題として挙げられています。
5.結論
この研究では、ゲーム型学習環境において「内省の質」が学習と問題解決の成否を左右することを実証しました。深い内省を促す鍵は、学習目標と直接結び付け、代替案の生成を迫るプロンプト設計と,適切な提示タイミングにあります。単なる振り返り機会の提供では不十分であり、「質を高める支援」と「マルチモーダルデータによる可視化」を組み合わせることで、学習者の戦略的思考を育成できると示唆されました。今後の研究では、個人差に応じた内省支援の最適化、および学習環境におけるリアルタイムな内省支援技術の開発が重要な課題となると考えられます。
以下は、私の感想になります。
内省はどのように学習成果と関係するか、及びゲームにどのように内省を組み込むことが効果的かという点について学びたいと思い、この論文を参照しました。
特に参考になったことは、内省の質が学習成果に関係するという点及び内省プロンプトの設計によって内省の質が左右されるという点です。この点について、内省は単なる評価でなく、問題解決能力を向上させるための有効な手立てとして、自分の研究にも組み込みたいと思います。
一方、内省の質と学習成果の関係については理解できましたが、プロンプト以外に何が内省の質の向上に影響するのか、といった点についてはやはり疑問が残ります。本文中には「学習行動ログを収集する」旨の記述がありましたが、学習ログと内省や学習効果との関連については深く言及されていませんでした。学習中の行動によって、内省の質が変化する可能性も考慮したいです。また内省の指示を与えるタイミングや頻度についても、どのように影響するかという点について気になっています。学習者への負荷や学習者の特性など、多角的な視点から考察できるように設計することの是非についても、今後注目して学んでいきたいです。
文責:尾﨑康平