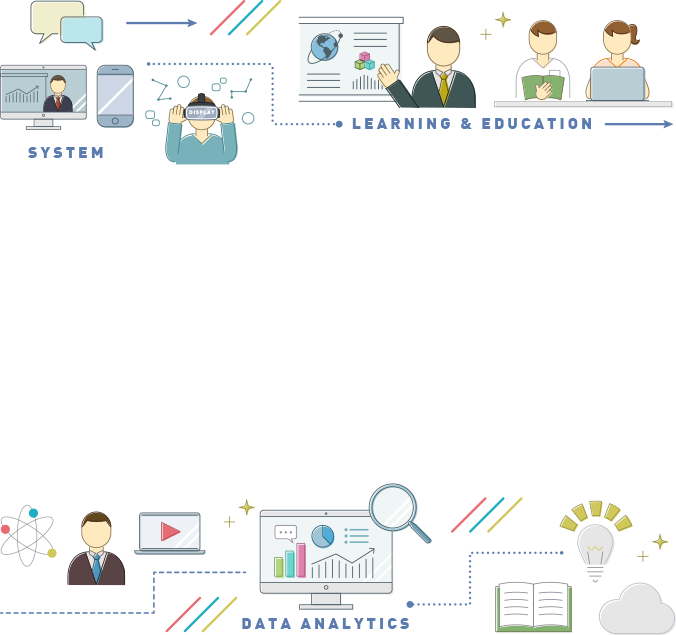皆さん、こんにちは。
この記事では、英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。
論文タイトル:Linking Career Exploration, Self-Reflection, CareerCalling, Career Adaptability and Subjective Well-Being: A Self-Regulation Theory Perspective
著者: Jingliang Ran, Huiyue Liu, Yue Yuan, Xuan Yu & Tiantian Dong
ページ: 2805-2817
出版年:2023
ジャーナル: Psychology Research and Behavior Management
研究の背景と目的
現代において学生たちは変化の激しい就職環境に適応する能力が求められています。
この論文では、学生へのキャリア支援における下記2つの重要な課題に取り組むためのアプローチを提示しています。
1. キャリアアダプタビリティ(適応性)の育成: 変化に柔軟に対応し、自らキャリアを構築していく能力
2. 主観的幸福感の育成: 人生における満足感を示す、人生全体に対する包括的な幸福度
研究の目的として、「キャリア探索」「自己省察」「天職意識」「キャリアアダプタビリティ」「主観的幸福感」といった、キャリア形成に関する5つの主要な変数がどのように関連し合っているのかを、構造方程式モデリング(SEM)を用いて分析しています。
理論的基盤:自己決定理論とキャリア発達の理論の統合
個人のキャリア発達における行動、認知、感情のメカニズムを理解するための強力な理論的枠組みとして、自己決定理論を採用しています。この論文では、自己決定理論の枠組みに、それぞれのキャリア発達変数を以下のように位置づけています。
1. 自己観察: 自らの行動やその成果、状況に関する情報を収集し、認識するプロセス
→キャリア探索:自己の興味・能力や外部の職業環境に関する情報を収集する行為
2. 自己判断: 得られた情報を、基準や目標、他者との比較に基づいて評価するプロセス
→自己省察:過去の経験や現在の状況を評価し、意味を見出す認知的な活動
3. 自己反応: 自己判断の結果に基づいて生じる、感情的・行動的な反応、動機づけなど
→キャリアアダプタビリティと主観的幸福感:自己観察と自己判断の結果として生じる内的な経験や適応行動
4. 天職意識(キャリアコーリング):自分の仕事や人生に深い意味や価値を見出し、強い内的な動機づけを持つこと。
→キャリア探索と自己省察という内省的プロセスが、天職意識の感覚を高める「先行要因」となり、それが間接的にキャリアアダプタビリティと主観的幸福感に影響を与える可能性がある。
設定された主要な仮説
上記の理論的枠組みに基づき、以下の仮説が設定されています。
1.キャリア探索は、キャリアの好奇心や関心を高め目標を明確化させるため、キャリアアダプタビリティを正に予測する。また自己省察は、自らの思考や行動を評価することで自己認識を強化し、自己調整を促すため、キャリアアダプタビリティを正に予測する。
2. キャリア探索のプロセスは達成感や満足感をもたらし、主観的幸福感を高める。自己省察は人生の意味感覚を高め、より高いレベルの主観的幸福感につながる。
3. キャリア探索および自己省察は、天職意識を高めることで、間接的にキャリアアダプタビリティと主観的幸福感に影響を与える。
研究の方法
この論文では、複雑な因果関係を検討するために、3週間にわたる3時点でのデータ収集と構造方程式モデリング(SEM)を組み合わせた量的なアプローチが採用されました。
調査対象は中国の大学生1077名で、回答データは3週間にわたって3時点で収集され、分析の結果、バイアスの影響は大きくないことが確認されています。
各構成概念(探索、省察、天職意識、適応性、幸福感)の測定には、先行研究で信頼性と妥当性が確認された既存の尺度(中国語版)が用いられ、各尺度の信頼性を示すα係数も高い基準(0.88〜0.97)を満たしているとしています。
研究結果と考察:探索と省察が天職意識を通じて成果に繋がる
提案された5因子モデルの適合度に関する値はχ2/Df = 2.92, CFI = 0.95,
TLI = 0.94, RMSEA = 0.04であり、良好な基準を満たしていたとしています。これを踏まえて、設定された仮説の検証が進められました。
1. キャリア探索と自己省察 → キャリアアダプタビリティ
2. キャリア探索と自己省察 → 主観的幸福感
上記において、有意な直接的な影響を与えていました。これは、自己の特性や外部環境を探索する行為、および自己の経験を評価し意味を見出す行為が、学生のキャリア適応能力と人生の満足度に直接的に貢献することを示しているとしています。
3. キャリア探索と自己省察 → 天職意識
天職意識 → キャリアアダプタビリティおよび主観的幸福感
この結果は、キャリア探索と自己省察が天職意識を高めることで、結果的にキャリアアダプタビリティと主観的幸福感を向上させるという媒介プロセスが明確に存在することを実証しています。すなわち、学生が内省的なプロセスを通じて天職意識という強い内的動機づけを獲得することが、変化の激しい社会に適応し、人生を満足して生きるための鍵となると、ここでは主張しています。
研究の限界と今後の展望
この論文では学生のキャリア構成に関する重要な知見を提供しましたが、筆者はいくつかの限界も存在すると述べています。
・外部環境要因の未考慮: 本研究は学生個人の内的プロセスに焦点を当てており、社会的支援や親のキャリア行動といった外部環境要因の影響を考慮していません。
・文化的な背景の影響: 対象は中国の大学生であり、古くから内省や省察の精神を重視する中国文化の文脈が、結果に影響を与えた可能性があります。
このため、今後は社会的支援などの外的要因をモデルに組み込むことや、異なる文化圏の学生を対象とした異文化比較研究を実施することが望まれていると示唆しています。
以下は、この論文を読んだ私の感想です。
自分の研究において、キャリア探索やリフレクションといったキャリアに関する行動とキャリアアダプタビリティや幸福感のような内的な資質や状態がどのように相互に影響する可能性があるのか? ということについて疑問に思い、この論文を読みました。
自分の視点では、キャリアアダプタビリティなどの内的資源がどう探索やリフレクションなどの具体的行動に結びつくか?ということに集中していたので、この研究において「行動がキャリアアダプタビリティや幸福感を高める」という方向の影響について確認できたことについて、非常に良い示唆をいただきました。相互に影響を与えたり、学習者の中でサイクルのようにキャリア自己調整を促進したりといった可能性も今後考えられると思います。
また、キャリアに関する項目と「自己決定理論」を統合し、キャリア発達を行動・認知・感情のメカニズムで捉えるという方法についても、参考になりました。特に「天職意識」という強い内的動機づけによってキャリア発達が媒介されるという結果が興味深いものでした。
一方で、評価の方法については疑問がありました。自己決定理論とキャリア発達の統合について、キャリアアダプタビリティを「感情的・行動的な自己反応」と位置付けていますが、これはキャリアに関する心理的な資源であり、自己決定理論と統合して実際の行動とみなして考察して良いかどうかについては議論の余地があると感じます。
今後、この研究の結果を参考にして、どのような介入や学習環境のデザインをすることによって、学習者のキャリア発達をサポートできるか、行動データや質的なアプローチなども取り入れた研究デザインを考えていきたいです。
文責:尾﨑康平