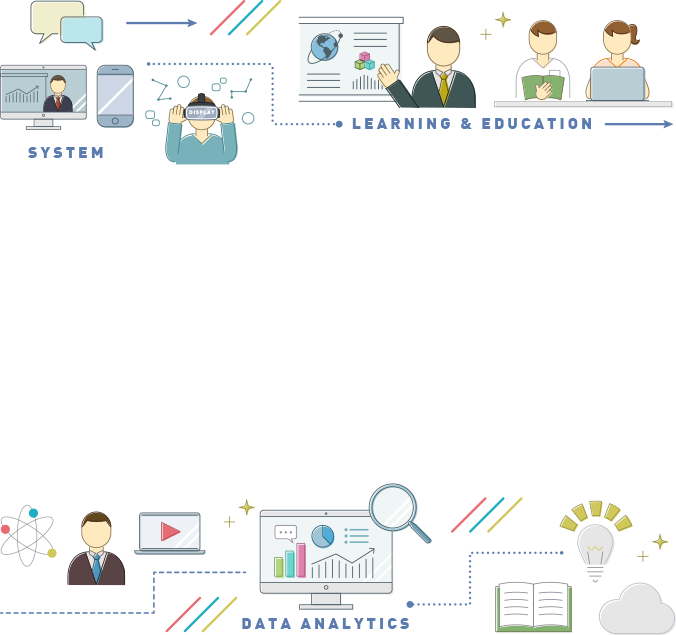みなさん、こんにちは。
先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介します。
論文タイトル: Interacting with ChatGPT in essay writing: A study of L2 learnersʼ task motivation
(エッセイライティングにおけ ChatGPTとの相互作⽤:第⼆⾔語学習者のタスクモチベーションに関する研究)
ジャーナル: ReCALL
出版年: 2025
著者: Javad Zare, Ahmad Al-Issa, and Fatemeh Ranjbaran Madiseh
1. イントロダクション
モチベーションは第二言語習得(Second Language Acquisition; SLA)において重要な研究テーマの一つです。中でも「タスクモチベーション」は、学習者の特性、学習環境、タスクの性質など複数の要因が動的に相互作用して生じる動機を指します。
英語のエッセイライティングは認知・言語・動機づけの負担が大きく、個別化された指導やフィードバックが不可欠ですが、クラス規模や多様なニーズのため十分に提供しにくいのが現状です。ChatGPTは即時・対話的フィードバックを提供でき、学習者中心の指導と整合すると考えられる一方で、L2学習者のエッセイにおける実証研究はまだ不足しています。
本研究は、ChatGPTとの相互作用がL2学習者の英語エッセイライティングに対するモチベーションに与える影響を、混合研究法により検証します。
2. 先行研究レビュー
2.1 SLAにおけるタスクモチベーション
モチベーションはSLAの成功を左右する重要な要因であり、学習者の行動を方向づける心理的原動力です。タスクモチベーションは、学習者特性や学習文脈、タスク構造の相互作用から生じるものであり、以下の三つの理論的枠組みで理解されています。
① 自己決定理論(Self-Determination Theory; SDT): 学習者の自律性・有能感・関連性という三つの基本的心理的欲求が満たされると、内発的動機づけが高まります。
② 自己調整学習(Self-Regulated Learning; SRL):学習者が自ら目標を設定し、進捗をモニターしながら学習に主体的に関与することです。SRLを促すタスクは、学習の主体性を高め、持続的な動機づけを支えます。
③ 学習者中心の指導:学習者の多様なニーズを尊重し、個別的で意味のある学習経験を促進する教育理念です。
2.2 論証型エッセイライティング、ChatGPT、およびタスクモチベーション
英語の論証型エッセイライティングは、推論や分析、アイデアの統合といった高次認知スキルを要するため、L2学習者にとって大きな負担となります。そのため、学習者が安心して書く力を伸ばすには、個別化された指導が重要です。ChatGPTのようなAIチャットボットは、深層学習に基づいて即時的かつ文脈に応じたフィードバックを提供でき、学習者中心の学びを支援するツールとして期待されています。
本研究では、ChatGPTとの相互作用がL2学習者の英語エッセイライティングへのモチベーションにどのような影響を及ぼすか、また学習者がどのようにAIとのやりとりを体験しているかを探ります。
リサーチクエスチョン:
RQ1:ChatGPTとの相互作用は、L2学習者の英語エッセイライティングに対するモチベーションにどの程度影響を与えるのか。
RQ2:学習者は、ChatGPTを用いた執筆経験をどのように捉えているのか。
3. 研究方法
本研究は、イランの公立大学英語学科における、逐次説明型混合研究として実施されました。
•参加者: 英語中級レベルの学習者69名(母語ペルシア語)が参加しました。
•デザイン: 事前テスト、介入直後事後テスト、および 1ヶ月後の遅延事後テストの 3 時点測定の統制群デザインが採用されました。
•介入: 指導は英語の論証型エッセイ全 12回で実施され、介入群は執筆のフェーズでスマートフォンを用い ChatGPTとやり取りを行いました。アイデアの洗練、コメント、語彙・文法・修正提案の支援のみが許可されました。比較群はピアワークを実施しました。
•測定: タスクモチベーションは、Ma(2009)による24項目・6件法質問紙で測定され、両群から各8名に半構造化インタビューが実施されました。
4. 結果
4.1 定量分析の結果
モチベーションの質問紙は 3つの時点で実施されました。
1. 事前テスト段階: 介入群の平均スコアは 91.67、比較群は 90.73 で、両群間に有意な差はありませんでした(p= 0.850)。
2. 即時事後テスト段階: 介入直後、介入群の平均スコアは 107.38 に達し、比較群(94.89)を統計的に有意に上回りました(p= 0.004)。効果量(Cohen’s d= 0.722)は中程度の影響を示しています。
3. 経時的変化(反復測定ANOVA): 介入群では、事前介入段階と比較して、即時事後テスト(p= 0.028)および遅延事後テスト(p= 0.015)の両方でモチベーションの有意な増加が確認されました。この効果が 1ヶ月後も持続したことが示唆されます。
4. 課題: 介入群のスコアは遅延事後テストでわずかに減少しており、ChatGPT の目新しさ効果や技術的補助への一時的依存の影響が示唆されました。
4.2 定性分析の結果
インタビューの分析の結果、モチベーション向上の要因として以下の 4つの主要なテーマが特定されました。
1. Progress (進歩) (38.89%): 最も頻繁に言及されました。エッセイ構成スキルや語彙力の向上を実感し、有能感が高まりました。
2. Support (サポート) (22.22%): ChatGPT を「常に利用できるチューター」として認識し、即時的なフィードバックが支援的な学習環境を構築したことが強調されました。
3. Enjoyment (楽しさ) (22.22%): ライティング課題が、ChatGPT の対話的で応答性の高い性質のおかげで「一種の楽しみ」に変わり、内発的動機が増加しました。
4. Individualized feedback (個別化されたフィードバック) (16.67%): 自身の具体的な問題点に特化したフィードバックを受けることで、メタ認知意識が高まり、改善につながったと感じました。
5. 考察
ChatGPTとの相互作用は、L2 学習者のタスクモチベーションを有意に高めた一方で、遅延測定での低下は、新奇性効果や支援への一時的依存を反映している可能性があります。この結果は、SDTやSRLの理論的枠組みと整合的です。しかし、長期的なモチベーション維持のためには、AI支援の活用と、学習者の自律的なライティング能力育成とのバランスを維持することが不可欠です。
授業設計においては、(1) AIからの提案に対する批判的評価基準を教えること、(2) フィードバックの理由付けや支援の漸減化(fading)により自律的方略の明示化を促すことが提言されています。
6. 結論
ChatGPTとの相互作用は、L2 学習者のモチベーションに肯定的で持続的な影響を与え、AI ベースのツールが支援的かつ適応性のある学習環境を構築する可能性を強調しています。しかし、遅延事後テストでのモチベーションの低下は、学習者の独立したライティング能力を育成することのバランスを維持する必要性を強く示唆しています。研究の限界としては、(1) イランの B1レベル EFL 学習者という限定的な集団であること、(2) モチベーションの測定が自己報告に主に依存していることなどが挙げられています。
7. 感想
本研究を選んだのは、自身の研究テーマとの関連性が高く、採用されている逐次説明型の混合研究法が自分の方法論とも合致しているためです。三時点で動機づけの変化を量的に追跡し、インタビューで背景を質的に深掘りするプロセスは大変参考になりました。
一方で、介入(ChatGPTの使用)が不明瞭である点は課題だと感じます。利用頻度、使用タイミング、対話回数、受け取ったフィードバックの種類などを明示することで、学習者間の個人差をより精緻に捉えることができると考えます。また、学習者の「進歩」については自己報告だけでなく、作文の評価を併用することで、より客観的かつ実践的な知見が得られると考えます。これらの示唆を踏まえ、今後の自分の研究をさらに発展させてまいります。
文責:田中 早代