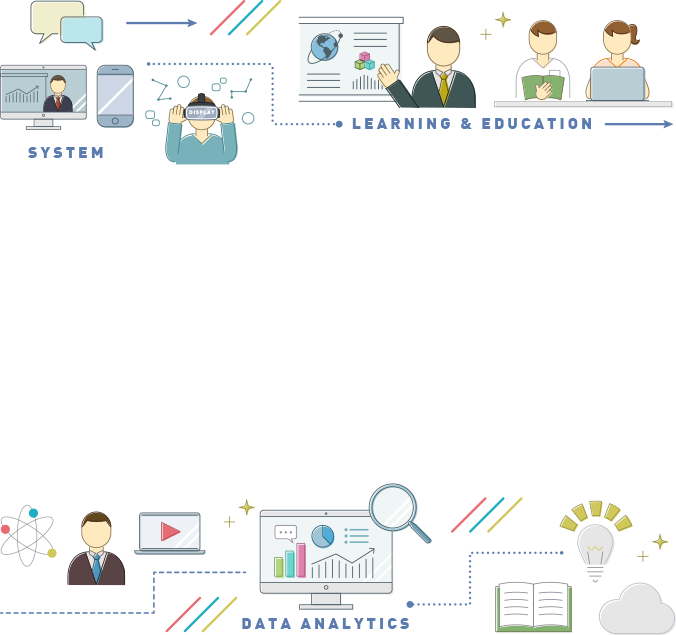皆さん、こんにちは。修士2年の樋口尚宏です。
この記事では、2025年10月23日の英語ゼミで紹介した論文のレビューをいたします。
今回紹介するのは、テクノロジーが普及する現代において、教師の日々の実践をどのようにデータで支援できるかを探究した研究です。具体的には、「学習データの分析」「授業のデザイン」「教師自身による探究」という3つのプロセスを、テクノロジーでいかに統合し、相乗効果を生み出せるかを論じています。
論文情報
・論文タイトル: Supporting teachers in data-informed educational design
・著者名: McKenney, S., & Mor, Y.
・出版: British journal of educational technology
・ページと巻号: 265-279, 46(2)
・出版年: 2015
複雑化する教師の実践と研究のギャップ
近年、「エビデンス(科学的根拠)に基づく教育」への注目が高まっていますが、学術研究の成果がそのまま多様な教育現場で使えるわけではありません。
先生方は日々、目の前の生徒の様子(データ)を見ながら、直感的に「授業デザイン」を行い、授業後には「振り返り(探究)」をしています。これらも本質的にはデータに基づいた実践です。
しかし、これらの実践は個々の経験や勘に依存しがちで、テクノロジーでデータを体系的に収集・分析する学術的なアプローチとは乖離がありました。本研究は、この研究者コミュニティと実践者コミュニティのギャップを埋めるため、以下の3つのキーワードに焦点を当てています。
1. Learning Analytics (LA); 学習分析:
学習者に関するデータを測定・収集・分析し、報告すること。学習そのものや学習環境の理解と最適化を目的とする。
2. Learning Design (LD); 授業デザイン:
授業設計のプロセスと成果物(指導案など)を、可視化・共有可能にし、デザインの質を高めることを目指す分野。
3. Teacher Inquiry (TI); 教師の探究:
教師自身が実践における「探究の問い」を特定し、証拠(データ)を収集・分析し、次の授業デザインに活かすプロセス。
これらLA、LD、TIは個別に研究されてきましたが、これらを統合し、教師主導で実践と探究のサイクルを回すツールや仕組みは十分ではないと本稿では指摘しています。そこでこの研究は、これら3つのプロセスに取り組む教師を、テクノロジーでいかに統合的にサポートできるか、そのツールの特性を明らかにすることを目的としました。
3つのプロセスを統合する「相乗効果」モデル
筆者らは、これら3つのプロセスが互いに影響し合い「Synergy(相乗効果)」を生むための理論モデルを研究の基盤としています。
このモデルの中心には「Rationale(理念)」が位置づけられます。これは、教育の目的、教室の状況、教師の教育的ビジョンや価値観といった、実践の根幹となる考え方です。
この「理念」を中核として、3つのプロセスが相互に作用します。LA(学習データ分析)の知見はLD(授業デザイン)の質を高め、LD(デザインのツール)はTI(教師の探究)の枠組みとなり、TI(実践の探究)の結果は次のLD(授業デザイン)の改善へとフィードバックされます。
研究の方法:CASCADE-SEAの回顧的分析
この研究は、過去に成功した事例から学ぶアプローチを取りました。
具体的には、1990年代に開発された「CASCADE-SEA」というソフトウェアプログラムに着目しました。これは、南部アフリカの中等教育(理科・数学)の教師を対象に、教材開発や専門性向上を支援するために広く使われた実績のあるシステムです。
CASCADE-SEAは、LA、LD、TIという現代的な用語が生まれる前に設計されましたが、その機能にはこれら3つの基礎的な要素が統合的に含まれていました。
そこで筆者らは、このシステムの設計・開発・評価の過程で収集された、4年間にわたる既存のデータセット(510名の参加者からのインタビューや質問紙など)を、LA・LD、TIという新しい視点から回顧的に分析(再コーディング)しました。
分析から見えてきたこと
データをLA、LD、TIの観点から再分析した結果、統合的ツールが持つべき重要な特性に関して、以下のような知見が得られたとしています。
1. Analysis (LA: 学習データ分析に関連)
・協働の重要性: 教師は多くの場合グループで協働するため、個人の作業だけでなく、グループでの協働をシステムがサポートすることが望まれていました。
・「Why(なぜ)」を問う思考の促進: 現状(What)を把握するデータ提示だけでなく、その原因(Why)を教師に問いかけ、思考を促す機能が重要だと示唆されました。
・継続利用の効果: システムはカリキュラム開発を学ぶ上で有用だと評価されましたが、その学習効果は、定期的に使用し続ける場合にのみ持続することも言及されました。
2. Design (LD: 授業デザインに関連)
・リソース(データベース)の価値: 過去のデザイン事例(指導案)や教材リソースをまとめたデータベースは、教師たちに非常に高く評価されました。
・省察の促進: システムの利用を通じて、教師は自身の教授実践について深く考えることを促されました。多くの場合、自身の教育哲学や価値観(=Rationale)について熟考するのは、これが初めての経験でした。
・共有への意欲: 教師たちは、リソースを利用するだけでなく、自身が作成したレッスン計画を提供したいという意欲を示し、他者の実践にコメントできるようなコミュニティ機能も望んでいました。
3. Evaluation (TI: 教師の探究に関連)
・ガイダンスの有効性: 授業の評価(探究)を計画・実行する上で、ステップ・バイ・ステップの具体的なガイダンスは高く評価されました。
・「ガイダンスと自由度」の緊張関係: 一方で、手厚いガイダンスは教師の思考を停止させる(怠惰になる)懸念があり、かといって自由度が高すぎると混乱を招きます。この「構造化」と「自由度」の適切なバランスが、ツール設計の重要な論点であることが示されました。
これからのツールデザインへの示唆
これらの分析結果から、筆者らは現代の統合的ツールが持つべきデザイン原則を提案しています。
その根底にあるのは、教育学者ドナルド・ショーンが提唱した「状況を作り出す教材との省察的な対話」というデザイン概念です。これは、教育者は学習者の成長を予測して活動を設計(デザイン)するが、その意図通りになったかは、実際に学んだ様子(データ)を確認して初めてわかる、という考え方です。
この概念に基づき、提案されたガイドラインの抜粋は以下の通りです。
・LAの原則: モバイル技術も活用し、対面(教室)のデータも収集できること。教師のグループ作業を支援し、「データをどう教育に活用するか」という観点でのガイダンスを提供すること。
・LDの原則: 過去の優れた教材デザインを参照できるデータベースを提供すること。デザインのプロセスに透明性と柔軟性を持たせ、チェックリストなどで作業を具体的に支援すること。
・TIの原則: 教師がデータをレビューし、実践への影響を省察し、結果を他教師と共有することを支援する機能。そして、画一的ではない、ユーザー固有のアドバイスを提供する仕組みを維持すること。
・相乗効果の原則: 最も重要なのは、LA・LD・TI間の「つながり」をシステムがシームレスに強化することです。そしてプロセス全体を通じ、中核となる「理念(Rationale)」を教師が継続的に見つめ直し、洗練させていくサポートを提供することです。
将来の展望と課題:「市民科学」としてのアプローチ
筆者らは最後に、このアプローチを発展させる方法として、「市民科学(Citizen Science)」のアプローチを提案しています。
これは、専門の研究者だけでなく、多数の教師が自身の教室でデータの収集・分析に主体的に参加するというビジョンです。そうして集約された膨大な現場からのデータが、科学的に有効な証拠の集合体を形成する可能性があります。
しかし、このビジョンを実現するには、教師が「データ探究者」としての考え方を持ち、実践するための時間やリソース、報酬が提供されるといった「文化とリソースの課題」や、多様な教室での研究結果をどう集約・統合するかという「方法論の課題」、そして学習者のプライバシーをどう保護するかという「倫理的な課題」が残されています。
感想
私が自身の開発研究で参考にしている理論が、まさにこの論文の流れを組むものだったため、今回はその理論に忠実に従って設計・実践されたシステム(CASCADE-SEA)に着目した本論文をレビューしました。
感想として、時代背景もあってか、LAにおける詳細なデータ活用の部分が少し弱いと感じました。元々このプログラムは教材開発が主目的だったためかもしれませんが、私の研究ではLAをもっと前面に押し出し、デジタル教材システムで得られる学習ログを活用した、より粒度の高い分析とリフレクションを可能にしたいと改めて思いました。
また、システムの中で教師の共同作業や知見の共有という観点が度々紹介されていたのは大きな収穫でした。私自身が開発するシステムも、将来的に教師がチームとして共通の課題や理念を設定し、それに対して授業実践や分析、知見の蓄積、議論ができるシステムとして機能させるのも面白そうだなと考えていたので、そのアイデアを補強する資料が得られました。
11月に参加するCLE研究会の原稿では私のシステムのプロトタイプの形成的評価が内容だったので、その執筆するうえで、今回の論文のシステムの背景理論、機能説明、理論に基づいた評価と議論、という論文構成の流れが非常に参考になりました。開発と理論のバランスを大事にしながら、今後の研究に取り組んでいこうと思います。
文責:樋口尚宏