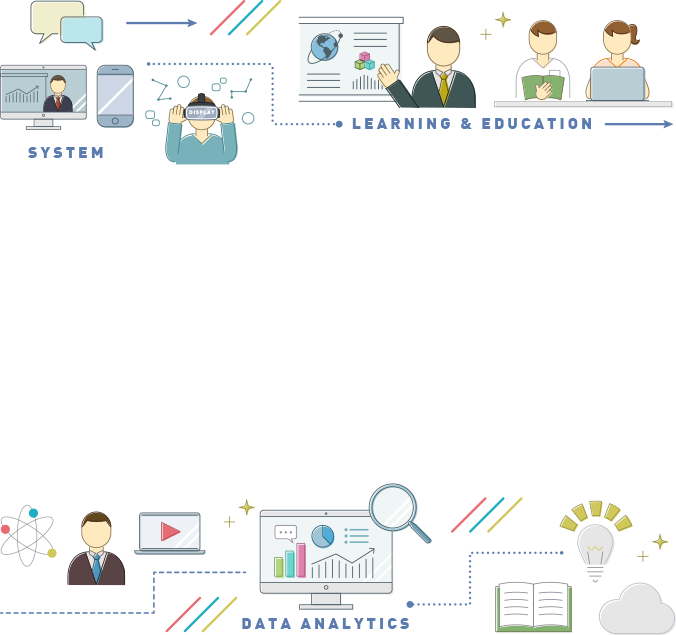EFLライティング指導へのLLM統合: ライティングスコア・自己調整学習方略・モチベーションへの影響とは?
みなさん、こんにちは。博士後期課程1年の田中です。
先日の英語文献ゼミで読んだ論文を紹介します。
論文タイトル:Integrating large language models into EFL writing instruction: effects on performance, self-regulated learning strategies, and motivation
著者名:Ze-Min Liu, Gwo-Jen Hwang, Chuang-Qi Chen, Xiang-Dong Chen & Xin-Dong Ye
ジャーナル:Computer Assisted Language Learning
出版年:2024
【イントロダクション】
英語を母語としない英語学習者にとって、ライティングは習得が難しい技能の一つですが、近年、自己調整学習(Self-Regulated Learning: SRL)方略を用いた指導が取り入れられています(Teng, 2022)。SRLとは、「学習者が自身の目標達成に向けて、動機づけ、認知、メタ認知、行動などを自律的にコントロールするプロセス(Zimmerman, 2000)」であるとされています。
学術的言語学習アプローチ(Cognitive Academic Language Learning Approach: CALLA)は、SRLの育成を促す方略指導モデルとして広く用いられてきましたが、教師の負担が大きく、学習者一人ひとりに個別対応することが困難であるという課題が指摘されてきました。そこで本研究では、大規模言語モデル(Large Language Models: LLM)をCALLAに統合した新たなモデル「CALLA-LLM」を開発し、その教育的有効性を検証しました。
【文献レビュー】
先行研究から、SRL方略がEFLライティングにおいて学習者のライティング能力と動機づけを高める重要な要素であることが示されています。学習者はライティングのプロセスにおいて、目標設定、自己モニタリング、内省、フィードバック活用などのSRL方略を活用することで、認知的負荷を軽減し、学習効率を高めることができます。これらの方略は、学習者の自信や興味を高める効果もあるとされています。
一方で、SRL支援において適応性や個別化が不十分であるという課題もあります。既存の支援ツールでは、学習者の実際のSRLプロセスに即した柔軟な支援が難しく、より個別化された支援の開発が求められています。
また、動機づけ、特に自己効力感と内発的興味は、ライティングの質や学習の継続に深く関わっています。高い自己効力感をもつ学習者は困難な課題にも前向きに取り組む傾向があり、興味が高ければより質の高いアウトプットにつながります。SRL方略と動機づけは相互に関連するため、両者を同時に支援する教育設計が必要です。LLMは個別化されたフィードバックの提供や方略のモデリング支援をリアルタイムで行うことができることから、近年その有効性が議論されており、AIと教師の協働を目指す「Humans in the Loop」の枠組みも注目されています。
【研究課題】
本研究では、以下3つの研究課題を設定しています。
1. CALLA-LLM群は、従来のCALLAに比べて、英語ライティング能力にどのような影響を与えるか。
2. CALLA-LLM群は、SRL方略の使用にどのような影響を与えるか。
3. CALLA-LLM群は、ライティングに対する動機づけ(自己効力感および興味)にどのような影響を与えるか。
【研究方法】
本研究は台湾の小学校6年生65名を対象とし、参加者は無作為にCALLA-LLM群(32名)と対照群(33名)に分けられました。両群ともに、5週間・全10回のプロセスライティング指導を受け、CALLA-LLM群にはGPT-4を活用したWebアプリによる支援が提供されました。
授業は、準備、提示、練習、評価、拡張の5フェーズで構成されるCALLAの枠組みに沿って行われ、CALLA-LLM群には各フェーズに対応するプロンプトとAPIが設定されました。評価には、作文課題(3回)、SRL方略に関する質問紙、ライティング動機づけを測る質問紙(自己効力感・興味)を用い、T0(指導前)、T1(指導直後)、T2(1か月後)の3時点で測定しました。統計分析にはjamoviを使用し、正規性、等分散性、初期群間差を確認し、主な分析手法として線形混合効果モデル(LMM)を用いました。
【結果】
CALLA-LLM群は、作文スコア、SRL方略の使用頻度、動機づけの全ての面で対照群よりも高い成果を示しました。作文スコアはT2で対照群より平均5.13点高く、文法・語彙、構成、一貫性の観点で特に有意な改善が見られました。SRL方略についても、計画、生成、推敲、モニタリングの全手に置いてT0からT2にかけて有意な得点向上が確認されました。
動機づけはCALLA-LLM群の自己効力感がT1とT2で有意に向上しました。一方、興味についてはT1で上昇したものの、T2では維持されませんでした。これは、LLMによる即時的支援が短期的な動機づけ向上には寄与する一方、長期的な内発的動機づけの維持は困難であることを示しています。
【考察】
CALLA-LLM群は、CALLAの構造化されたスキャフォールディング(学習者が一人でできるようになるまでの教師や支援者などによる一時的な支援)とLLMによる即時性の高い支援を融合することで、学習者にとっての最適な支援を可能にしました。SRLは適切な指導環境の中で育まれるスキルであり(Zimmerman, 2000)、本研究では、CALLA-LLMモデルがその発達を促進する役割を果たしたと考えられます。
CALLA-LLMはライティングにおける複雑なSRLのプロセスに柔軟に対応でき、学習者の実際の行動に基づいたリアルタイムな支援を行う点で、従来の方法より適応的で優れています(Lim et al., 2021)。また、CALLA-LLMモデルは段階的かつ個別化された支援を実現しており、計画・生成・推敲・モニタリングといったSRLの主要な方略が連動して効果的に機能したと推察されます(Flower & Hayes, 1981)。
一方、LLMは学習者の自己効力感の向上には効果的であるが、内発的な興味を持続的に高めることには限界があることが示されました。今後の研究では、内発的動機づけの維持を目的とした、動機づけプロファイルの導入、ゲーミフィケーションの活用などの工夫が求められます。また、LLMの支援が常に適切であるとは限らず、一部の学習者は混乱や不満を感じたことも報告されています。そうした場面では、教師による認知的・情意的介入が重要な役割を果たしました。この点からも、AIと教師の協働による支援設計、すなわち「Humans in the Loop」の枠組みの重要性が改めて浮き彫りになりました。
本研究の限界としては、調査対象が比較的英語力の高い一つの小学校に限定されているため、結果の一般化に限界があること。また、質問紙による量的データのみに基づいており、教師の介入などの定性的側面が未検討であることが挙げられます。今後は、より多様な教育環境における検証や、動機づけの持続に着目した長期的研究が求められます。
本研究は、LLMと教師の協働により、学習者のライティング能力とSRL方略、動機づけを高める新たな教育モデルの有効性を実証的に示し、今後のEFLライティング教育におけるLLM活用の可能性を拓く知見を提供しています。
【感想】
本論文を選定した理由は、自身の研究テーマとの共通点が多く、先行研究から明らかになっている知見と課題を整理・特定することができると考えたためです。また、山田先生よりご指導いただいている、「先行研究をクリティカルな視点で読む力」を養うことも目的の一つです。
本研究は、CALLAにLLMを統合した新たなモデル、「CALLA-LLM」を開発し、従来のSRL方略指導の枠組みを拡張するとともに、個別最適化された新しい支援モデルの有効性を検証している点に新規性があると考えました。一方で、課題としては、「研究の限界」にも示されているように、学習者のCALLA-LLMに対する反応や教師の介入のあり方など、学習プロセスに関する定性的データが欠如している点が挙げられます。例えば、「学習者が混乱や不満を抱える場面があった」と述べられていますが、どのような具体的な問題が生じ、教師がどのような認知的・感情的支援を行ったのかについての詳細な記述はありません。また、本研究は小学生を対象としていますが、それらの課題が年齢的要因によるものか、英語の習熟度に起因するものかは明確ではありません。
本研究が重視している「Humans in the Loop」の実現に向けては、LLMと学習者、教師との相互作用のメカニズムを質的に検証することも今後の重要な課題であると考えます。さらに、なぜ研究対象として小学生を選定したのか、また、なぜCALLAモデルを基盤としたのかという理論的・実践的背景の説明も不十分であるように感じました。
ゼミのディスカッションでは、「SRL方略を質問紙で測定しているが、SRLにおける『リフレクション』の観点が含まれていないのではないか」、「ライティングへの内発的興味を持続させるために必要な支援は何か」といった問いに関する議論も行いました。
本研究から得られた知見や課題を今後の自身の研究に活かしていきたいと考えています。
文責: 田中