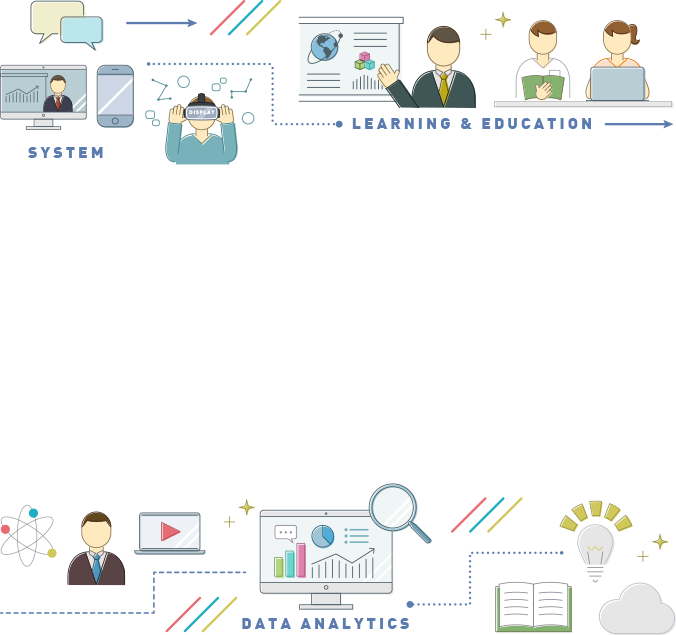皆さん、こんにちは。
この記事では、今回の英語文献ゼミで読んだ論文とその感想について紹介します。
論文タイトル:Does Gamification Influence Students’ Online Learning Behaviors and Academic Performance?-A Learning Analytics Perspective-
ジャーナル:International Conference on Smart Learning Environments
出版年:2023
ページ数:127-138
著者名:Mustafa, M. Y., Tlili, A., Qazi, A. G., Huang, R., & Adarkwah, M. A.
研究の背景と目的
高等教育機関では、COVID-19の影響でオンライン授業が急増し、学習管理システム(LMS)が広く使われるようになりました。しかし多くの学生はアップロードされた教材を閲覧するだけで終わってしまい、理解が不十分なまま質問が増えるなど、LMSの活用が十分とは言えない状況です。そこで、この研究ではゲーミフィケーションを取り入れてLMSへの参加意欲を高めることをねらいとしており、具体的には以下の2点を目的としています。
⒈ ポイント、バッジ、ランキング、レベルアップなどの要素を加えたゲーミフィケーション型LMS(GLMS)を開発し、学生の学習行動と教員とのインタラクションを活性化させること。
⒉ GLMSで得られるログデータにラーニングアナリティクスを適用し、ゲーム要素の導入が学業成績にどう結びつくかを評価すること。
GLMSの主な機能
ゲーミフィケーションとは、ゲームでおなじみのルールや報酬を教育等の場面に取り入れることであり、この論文では自己決定理論(「有能感」「自律性」「つながり」の要素)をもとに、学生が自ら学習を進めたくなる、以下のような仕組みを設計しています。
・アクティビティポイント:動画視聴やクイズ回答など各行動に点数を付与し、リーダーボードで表示する。
・バッジ:達成項目ごとに称号を与え、達成感と競争意識を刺激する。
・レベル:獲得ポイントに応じて「Newbie→Mediocre→Expert」と段階的に成長を実感させる。
・フィードバック:教員が週ごとにコメントを投稿し、学習理解をサポートする。
・アバター編集:自分のキャラクターを自由にカスタマイズ可能にし、愛着を促進する。
・ディスカッションフォーラム:投稿や返信にポイントを与え、学生同士の交流も活発化する。
研究の方法
この研究は、パキスタンの公立大学4年生の「Data Structure」という講義の履修者204名を対象として行われました。そのうちGLMSの利用者は104名(実験群)、従来から使用されている非ゲーミフィケーション型のLMS利用者は100名(対照群)でした。期間は5週間で、両グループとも同一教員が同一教材を毎週アップロードしました。
収集したデータは「ログイン」「講義閲覧」「理解度提出」「ページ訪問」「メッセージ閲覧」「プロフィール変更」6種類の行動ログでした。
データの分析
収集した約7,200件(GLMS)と3,151件(従来LMS)のログを、SPLUNKツールで可視化・集計、講義アップロード直後の閲覧数やフォーラム参加状況を比較し、さらに理解度ポイントと最終成績の相関をPearson分析で検証しました。主な結果として、以下のようなことがわかりました。
・ 講義閲覧:アップロード直後の教材閲覧数はGLMSがTLMSを大幅に上回り、継続的な関与が促進されたことが確認できました。
・ フォーラム参加:フォーラム参加の回数が多い学生ほどテスト成績が高く、投稿・返信への参加が学業成績の向上と関連している可能性が示唆されました。
・ 理解度提出と成績の相関:理解度を報告してポイントを獲得した学生ほど期末成績が高い傾向があり(r=0.381、p<0.05)、適時の自己評価が学習成果に結びついていることがわかりました。
考察と今後の課題
この研究によって、ゲーム要素は「講義公開直後の関心喚起」に強く効果を発揮し、教材閲覧の活性化に寄与することがわかりました。さらにフォーラムなどの対話機能は、学習内容の定着だけでなく仲間との協働学習を促し、結果的に成績向上に結びつく可能性があることも示唆されています。理解度提出(自己評価)の仕組みについては、教員の指導を受ける前に自分の理解をチェックする習慣を育て、学習成果を高める手助けになります。
総じて、LMSへゲーム要素を付与することで学生の参加率やエンゲージメントを高め、学習成果にも影響することが考えられます。
一方で、各機能の個別の学習への影響についてはまだ検証する余地があります。どの機能がどのように作用したか、また教員の関与の仕方などの要因との関連についても、今後の課題として残されています。
以下は、私の感想になります。
ゲーミフィケーションを用いた授業設計とラーニングアナリティクスを統合する設計や効果、評価について学びたいと思い、この論文を読みました。教材でなくLMS自体にゲーム要素を付与することで、学習行動や学習成果に影響できるという点で、授業デザインの視点から参考になりました。
一方で、以下の点について、今後調べる必要があると思っています。まず、結果の部分で教材閲覧については「アップロード直後の」閲覧数に限定されて分析されており、論文中の表からは、教材の閲覧回数について日が経つにつれて閲覧数に差がなくなっているようにも読み取れます。ゲーミフィケーションでは繰り返し学習することにはつながらないのか、それとも早期に教材を閲覧することで十分に学習できたと学習者が判断したのかということについては疑問が残りました。また、ゲーム要素の種類やタイミングによって効果が異なるという可能性があるため、最適なデザイン条件の検討についても考慮する余地があります。
あわせて、そもそも「ゲーム要素」というものがポイントやバッジ、レベルなどを設定することのみで語ることができるのかという点についても考えていきたいです。本文中には「追加される各ゲーム要素は遊び心を意図していなければゲーミフィケーションと呼べない」という記述があり、実際には学習者の課題や教材の特徴、学習形態(集団・個別・オンラインなど)によってどのような場面でどういったゲーム要素が有効なのか、また効果が薄いのかということについて複雑な影響がありそうだと予想できます。今後はより全体の学習デザインに応じた教材やLMSの開発について調べていきたいです。
文責:尾﨑康平