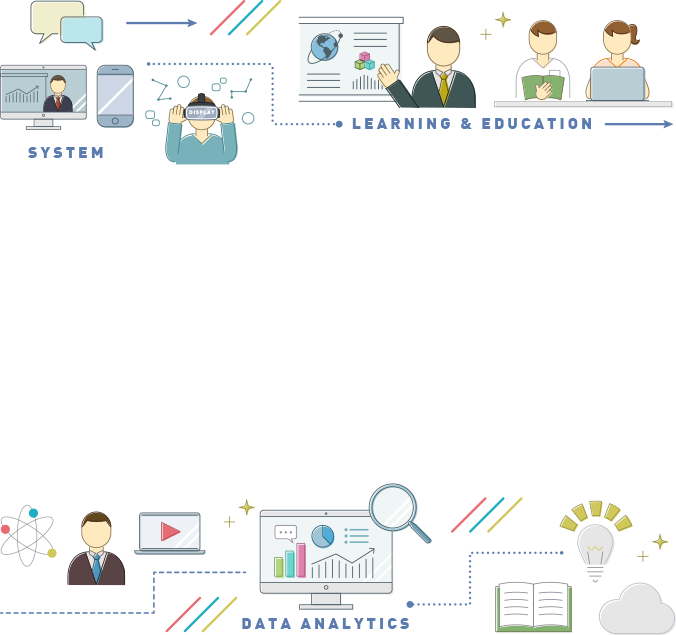皆さん、こんにちは。修士2年の樋口です。
去年の9月からトルコへ交換留学に行っていたのですが、6月に戻ってまいりましたので、これからまた山田研究室で研究を頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この記事では、今回私が英語文献ゼミで紹介した論文のレビューをいたします。
論文情報
タイトル:Mediating Teacher Professional Learning with a Learning Analytics Dashboard and Training Intervention
出版:Technology, Knowledge and Learning
ページ:981-998
出版年:2023
著者名:Khulbe M & Tammets K
背景
近年、国内ではGIGAスクール構想の影響などで学校現場のデジタル化が進んでいますが、海外でも教育現場でデジタル技術を活用して多様なデータを収集して学習や授業に役立てようとする動きが活発になっており、データに基づいた教師の意思決定への需要と期待も高まっています。
このような流れの中で、今回の論文の筆者たちは、「効果的なデータ活用のためには教師は新たな教授的、技術的、そしてデータに関する知識と活用スキルを獲得しなければならない」という点に着目し、エストニアの現役高校数学教師を対象に8ヶ月のデジタルリテラシー研修プログラムを実施し、そこでの知見をまとめたうえで効果的なLAD(ラーニングアナリティクス・ダッシュボード)のデザインを提案しています。
研究課題
本研究では「データリテラシー」と「生徒のエンゲージメント」という2点が主要な焦点となっています。データリテラシーについては「指導段階を決める手がかりとするために、多様なデータの収集、分析、解釈することで、情報を実行可能な指導的知識と授業実践に変換する能力 (Mandinach & Gummer, 2016)」という定義が使用されており、生徒のエンゲージメントに着目した理由としては、学習成果の予測や達成と強い関わりがあることが認められていることを理由としています。また、エンゲージメントの中でも、1) 行動的(学習時間、課題達成など)、2) 認知的(深い理解、学習目標のための適切な戦略の使用など)、3) 感情的(学習に対する感情)、4) 主体的エンゲージメント(活発な学習活動への参与)の 4つの種別を考慮しています。
本論文での研究課題は以下の3つです。
RQ1: 研修プログラムは、数学の授業で生徒のエンゲージメントを測定するうえでの教育データの重要性について、教師の理解の向上をどの程度支援したか。
RQ2: 研修期間を通じて、教師のデータリテラシーはどの程度変化したか。
RQ3: 教師向けのデータリテラシー研修を設計する際に、どのような設計原則を考慮すべきか。
方法
RQ1, RQ2の検証にあたって、8ヶ月間の数学教師向けの研修プログラムである 「the Teacher Innovation Laboratory」が実施され、教師に対するデータ活用についてのアンケート調査(量的分析)やリフレクションの参照(質的分析)によって結果がまとめられました。このプログラムでは21人の現役高校教師が参加し、月に一度の研修では、講師による教師のデジタルリテラシー向上のための講義や、他の教師とともにエンゲージメント向上のための授業計画の共同作成が行われ、次の研修まで各教師は作成した授業計画を実施し、次の研修ではその知見の共有が行われました。生徒のエンゲージメント確認には「LAPills」というアンケートアプリが活用され、教師はアンケートの配布、生徒からの回答収集、結果の確認をすることができました。また、RQ3は研修プログラムで得られた知見に基づいて設計についての議論が行われました。
結果と議論
データについての教師の捉え方の報告
教授におけるデータの有用性についての教師の捉え方の質問紙調査の結果、事前事後の数値でで有意な向上が認められました(事前M=3.75,事後M=4.02,t(11)=-2.59,p=.02.)。また、質的な分析のため、「LAPillsの結果にどの程度同意したか、またそれらの結果から何を学んだか」という質問に自由回答しました。分析の結果、教師は「新たに計画した授業の実施の中で普段より生徒が興味を示していた」などの、LaPillsを使わなければ見逃したであろう有益な洞察を得ていることが確認されました。
教師のデータリテラシーのスキル
以下の4つの観点で、研修プログラムを通じた教師のリテラシースキルについての結果の確認と議論が行われました。
1. データ選択と収集のスキル:質問紙を用いて、研修プログラムを通じて適切なデータ選択・データ収集ができるようになったかについてを調査した結果としては、選択と収集両方で事前事後の有意な数値の上昇が確認されました(選択:事前M=2.35, 事後M=3.12, t(16)=-3.05, p=.007.;収集:事前M=2.29, 事後M=3.35, t(16)=-4.24, p<.001.)。
2. データ解釈スキル:教師のデータ解釈と教授活動への転換能力を評価するため、教師のリフレクションが分析されました。結果として、ほとんどの教師が生徒のエンゲージメントを正確に特定するためにデータを活用していたことが確認され、特に認知的エンゲージメントへの注目が高かったことが確認されました。
3. データに基づいた教授行動の実践:ほとんどの教師は、認知的エンゲージメントにおける課題を確認したにとどまりましたが、2人の教師は、自身が発見したエンゲージメントにおける課題に基づき、より深い学習体験を促進するための具体的な戦術についても言及していました(例:概念のリフレーズをもっと頻繁に取り入れる、概念理解のための議論を授業の終わりに取り入れる)。
4. 教師が直面した障害:生徒のエンゲージメント確認のために使用されたLAPillsの使用に関して、ほとんどの教師は収集されたデータの解釈をすることができていましたが、一部の教師は、解釈の困難性(2人)、データ表示の視認性の低さ(1人)、カスタマイズ性の低さ(1人)を訴えていました。
研修プロジェクトでの知見に基づいたLADデザイン
筆者らは、研修プロジェクトの結果から「将来の指導計画を立てるために新たな教授知識とデータから抽出された情報を紐づける能力は十分に確認することはできなかった(特定のデータに注目したにとどまる)」という課題を発見し、この課題の解決のために、明示的に教授設計要素(例: 生徒のエンゲージメント等)と研修で学んだ教授知識、そして実際に教室で得られたデータを結びつけ、教師の専門性の発達の足場架け(段階的な成長の援助)をするために、理論に基づいたLAツールの設計を提案しました。LAツールとしては、学生の学習についての深い理解のために近年活用が増えているLAD(ラーニングアナリティクスダッシュボード)に特に焦点が当てられており、以下の3つの設計における考慮要素が提案されています。
1. 教師の学習の足場架けにおける理論に基づく LA ツールの有用性:
効果的な教授・データ活用スキルの獲得を支援するために、LAツールは戦術的に段階を設けた足場がけを提供するべきであるとされています。筆者らの研究では、教授において重要な生徒のエンゲージメントに関わる情報の説明と、教授知識とデータ活用スキルの発達を目指すために推奨される、教育理論に基づいた教授実践提案が通知されるとのことです。
2. LAツールの理論基盤:
教師の足場がけや教育データ(本研究ではエンゲージメントに関連したデータ)を活用したLAツールの設計を行うにあたって、その基盤は関連する理論でなければならないと主張されています。
3. 複数のデータソースの使用:
本研究における主要なデータソースはLAPillsによる生徒の自己報告でしたが、生徒のエンゲージメントという複雑な現象のより深い理解のために、より多様なデータの活用が推奨されています。
結論
本研究ではK-12の数学教師を対象としてデータ活用の課題に対して、教室でのデータと実践を取り入れた協働的な研修介入のプログラムが行われ、結果として、ほとんどの教師がデータ利用に対して前向きな態度を示した一方で、データの表示方法についての課題や、大多数の教師がデータから得られた発見に基づいて適切な教育行動を選択するという段階にまで達することができなかったという課題が見られました。また、実践で得られた知見をもとに、筆者らは教育理論に基づいて教師が教育的知識とスキル、そして教室で得られたデータを結びつけて適切な授業実践に移す学びの足場となるLADの提案も行われました。
感想
私が今後行ってく研究が教師のデータに基づいた教師のリフレクションを促進する LAD の開 発なので、非常に近い研究をレビューして研究における理論背景や評価方法などの知見を深めたいと考え、本論文を選びました。
レビューの感想としては、8ヶ月という⻑い時間を設けて、現場の先生方とともに実践を継続的に行った点で現場に根ざした素晴らしい研究だと感じた一方で、LAD についてのデザイン提案もありましたが、研究として実際に行われたのは研修介入までだったため、具体的なイメージが湧きづらいところがありました。また、提案されたLADでは、教室から得られるデータや関連する教授理論などを考慮して注目すべき情報の表示とそれに基づいた適切な教授行動の提案までがなされるとのことでしたが、LAD内で提案する行動は、たとえ元にする教育理論があったとしても教室文脈や学校・自治体の制約やその他のリソースなどの要因にも大きく左右されるため、一般化して事前に定義をするのはすごく大変そうだと感じました。理論と教授行動の折り合いをどのようにつけて現場で導入していくのか、これからの研究に期待したいと思います。
文責:樋口尚宏