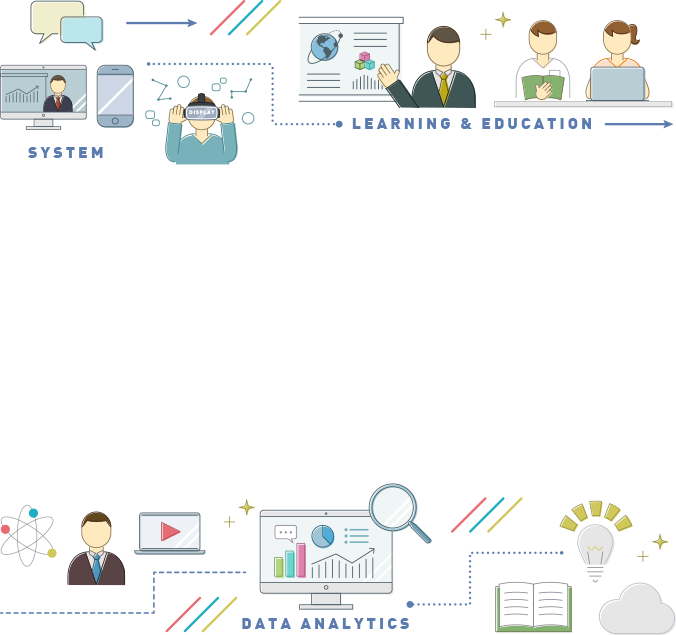大きくニュースに出ていましたね。福岡女子高校、共学化へ検討開始と。
NHK福岡「市立福岡女子高校が27年度に共学化 県内全公立高校が共学に」
KBC「福岡女子高校の共学化検討 実施されれれば公立女子高校は県内ゼロへ」
専門学科を有する市立高校のあり方を検討する市の有識者会議にて、会長という役割を賜り、様々な領域の専門家の皆様と様々な観点で議論を行い、共学化という方向性について提言を致しました。全国的に専門学科をもっている高校が学生獲得など苦戦をし、総合学科へ転換していること、福岡市内でも福翔高校が総合学科という形で展開しているという実績、さらに福岡女子高校について競争倍率が1を切ってしまっている学科が多いこと、急激な社会状況の変化への対応というところで、専門学科を有する高校をこれからどうしていけばいいか、提言をしました。
市教委さまより議会へのご説明がありましたが、その1週間前くらいに、なぜかこのニュースが流れてしまって、複数のテレビ局さまから私へ取材という形で来たのですが、お受けできず申し訳ありませんでした。取材を仮に受けたとしても、私から話せることはないんですよね・・・有識者会議は「提言」としてまとめたに過ぎず、市教委さまや市議会のみなさまが報告書の内容を踏まえて、今後、決定をいろいろされていくのだと思います。
ただ、注意したいのは「共学化」というのは目立ちますし、そっちに意識が働くのですが、そこは1つの過程に過ぎず、本質はもっと違うところにあるのだろうと私は考えています。実際に報告書の中でも共学化以外のところも記載しています。共学化すると、単純に女性以外も受験できることになるので、受験者の母数は増えるわけですけど、学校自体が魅力ある形に変わらなければ、また同じことになるのだろうと思います。生徒さん、保護者さん、中学校の先生とか、関係者が魅力を感じる学校にしていかなければならないと思います。
福岡女子高校は服飾デザイン、保育福祉、食物調理、生活情報、国際と、専門学科があるのですが、これらは非常におもしろいコンテンツだと考えます。これを今の時代の潮流に載せて、どう位置づけて、カリキュラム化、授業へ展開していくか?ですね。どういう人材を育成していくのか、そのあたりのコアコンセプトから見直して、大学の3ポリシーじゃないですが、それに似た形のものを作って、考えていくとか必要だと思います。また専門学科を中心とした学びは探求と相性がいいなと思います。服飾デザイン、保育福祉、食物調理、生活情報、国際、それぞれ社会と密着しているわけですから、これらと数学、社会化、国語、英語、理科系、芸術系、保健・体育とクロスドメインで探求学習を進めるというのは非常におもしろい授業になるのではないかと思います。たとえば経済産業省「未来の教室」実証事業で行われていた、Z会の取組などは専門学科 x 他教科 x ICTの事例として非常に参考になると思います。ただこれを通常授業にどうやって落とし込むのか、ただでさえタイトなカリキュラムにどう対応していくのか、ここは検討が必要になるかなと思います。そういう課題を感じつつも、非常に参考になると思います。専門学科で扱っている内容というのは、まさに現実、これほど社会と密着した社会課題、場合によっては地域課題となるわけですから、この課題を教科と組み合わせて考えるというのは非常によい学びになると思います(もちろん、授業設計次第ですけど)。
山田研の研究でも、地学 x 生物 x 化学 x 数学 x 地理を掛け合わせたSTEM型授業、生物 x 保健を合わせた感染症予防に関する探求型授業を行いましたが、学習成果も向上し、どういう観点で授業デザインすべきか、データサイエンスのアプローチで検討しました。非常に可能性を感じる授業でした。こういうアプローチも活用することでよりよい授業、カリキュラム、学校を創っていくことができるのではないかと思います。
これはただ、女子校を共学化したというレベルではなく、様々なものが手の中にあるスマートフォン、生成AI(ですらスマホのアプリ)で情報が手に入り、行動を起こせる社会で、どういう学びの場をデザインしていくのか、考えていかなければなりません。キーコンピテンスになるものは何かを見極め、それを3年間、継続して練り上げていくものと教科、教科横断型授業と組み合わせていくなど、いろんなアプローチがあり、検討すべき大きなタスクになるはずです。
これまで福岡市立高校とは福岡市教育委員会と共同でデータ駆動型教育の実践研究など行ってきましたので、陰ながらでも、これからの福岡、日本を支える人材育成に向けて、お手伝いできることがあればうれしいです。