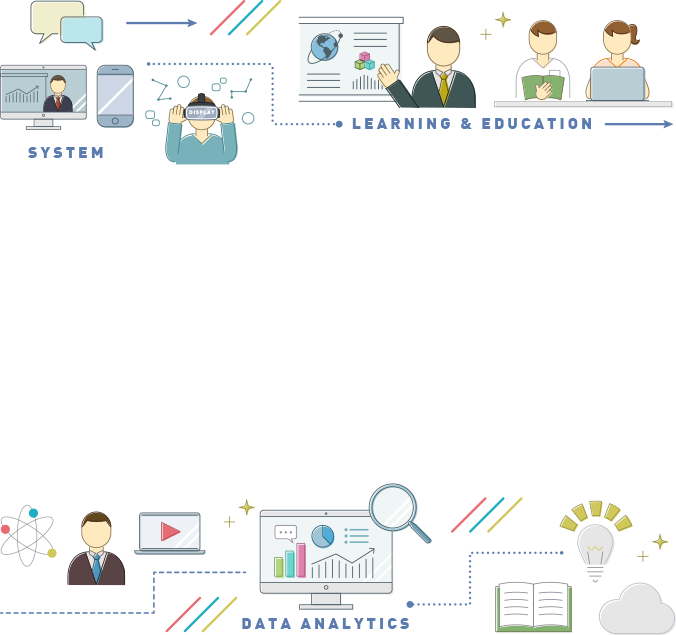山田研究室メンバー
修了生・山田研究室に所属された方々
渡邊 浩之(テクニカルスタッフ: 2019年10月-2022年3月)
現在、熊本大学 教授システム学研究センター 客員研究員
本研究室在籍時にはラーニングアナリティクスに基づく学習スキル・学習支援スキルの同定研究に従事した。
陳 莉(2021年12月修了: 2021年10月ー2022年3月:学術研究員) 博士(教育学)
九州大学、基幹教育員 学術研究院、大学院システム情報科学研究院 助教を経て、2025年4月より大阪教育大学 講師
修士・博士課程を通じてCollaborative Problem Solving-based STEM Instructional Design based on Learning Analytics(ラーニングアナリティクスに基づく協調的問題解決型STEM授業のデザイン)に関する研究を行なった。CELDA 2020にてBest Paper Awardを受賞
CELDA 2020 Best Paper Award受賞
耿 学旺(2024年2月修了) 博士(教育学)
九州大学データ駆動イノベーション推進本部 特任助教、 特任准教授を経て、崇城大学 情報学部 准教授
修士・博士課程を通じてARを活用した日本語複合動詞学習支援システムに関する研究を行なった。
CELDA 2025 Best Paper Award受賞
郝 皓(2024年12月修了)博士(教育学)
現在、新華社通信(中国)勤務
博士後期課程ではICTを活用した日本語CLIL授業のインストラクショナルデザインに関する研究をおこなった
江藤 真美子(2017年3月修了(修士))
福岡市養護教員を経て、2025年4月より西南女学院大学 講師。博士(医学)(佐賀大学)
修士の頃の研究として初等中等教育における、知識構成型ジグソー法を用いたヘルスリテラシー育成に関する研究に従事
大学院人間環境学府長賞 最優秀賞 受賞
唐 霏爾(2017年3月修了(修士))
GPSを用いた英単語学習ゲームのデザインと評価に関する研究
濵田 さとみ(2020年3月修了(修士))
株式会社ベネッセコーポレーション(Classi株式会社)を経て、現在、京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 緒方研究室 博士後期課程学生
修士の頃の研究は中学校における数学証明問題に関する学習支援システム開発に従事
馮 宣淇(2021年3月修了(修士))
現在、株式会社アピリッツにて勤務
修士課程ではインフォーマルラーニングにおけるゲーム型学習環境のラーニングアナリティクス基盤の開発研究を行なった(SSCI Journal “Journal of Educational Technology & Society” (Impact factor: 2.086)採択)
徐 宇凡(2021年9月修了(修士))
現在、Zhejiang Jiaxing Digital City Laboratory Company Limited(中国)にて勤務
修士課程ではグループディスカッションに伴う学習活動の可視化システムの開発と評価に関する研究を行なった
平田 沙希(2024年3月修了(修士))
現在、ALL DIFFERENT株式会社(旧株式会社ラーニングエージェンシー)にて勤務
修士課程では音声認識技術と自己調整学習支援を踏まえた音声記憶方略活用による英単語学習支援システムの開発と評価に関する研究を行なった
(Learning Analytics and Knowledge 2024(CORE Ranking AならびにGoogle Scholar Matrix in Educational Technology #20(2024年時点))にてHonorable Mention Poster Awardを受賞)
李 瑭(2024年9月修了(修士))
現在、株式会社NTTデータインフォメーションテクノロジーにて勤務
修士課程ではVRを活用した日本語オノマトペ学習支援システムの開発と評価に関する研究を行なった(IEEE Access誌(Google Scholar Matrix #1 in Engineering and Computer Science(general) )(2025年時点)に論文採択)
共同研究者・学術研究員・スタッフ
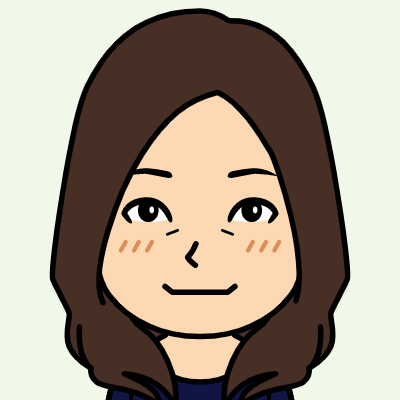
テクニカルスタッフ
芥川利恵
-
研究・業務内容
研究プロジェクト「教育データリテラシーモデル構築と関連システム開発」の研究支援

共同研究者:崇城大学 情報学部 准教授
-
研究・業務内容
・ラーニングアナリティクスに関する研究
・VRを活用した感情把握を踏まえた学習環境デザイン・開発
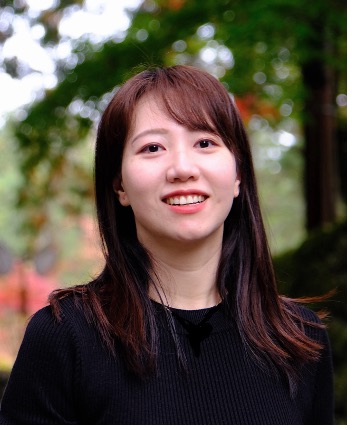
共同研究者:大阪教育大学 講師
陳莉
-
研究・業務内容
・生成AIに基づく、ラーニングアナリティクスを活用した知識マップ生成に関する研究
・協調的問題解決学習を活用したSTEM教育に関する研究

共同研究者:秋田大学大学院理工学研究科 助教
Lu Min
-
研究・業務内容
・ラーニングアナリティクスと統合したデジタル教材配信システム開発研究
・学習行動可視化システム"Reading Path"の開発研究

共同研究者:九州大学情報基盤研究開発センター 准教授
谷口雄太
-
研究・業務内容
・ラーニングアナリティクスと統合したデジタル教材配信システム開発研究

共同研究者:九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授
大久保文哉
-
研究・業務内容
・ラーニングアナリティクスと統合したデジタル教材配信システム開発研究
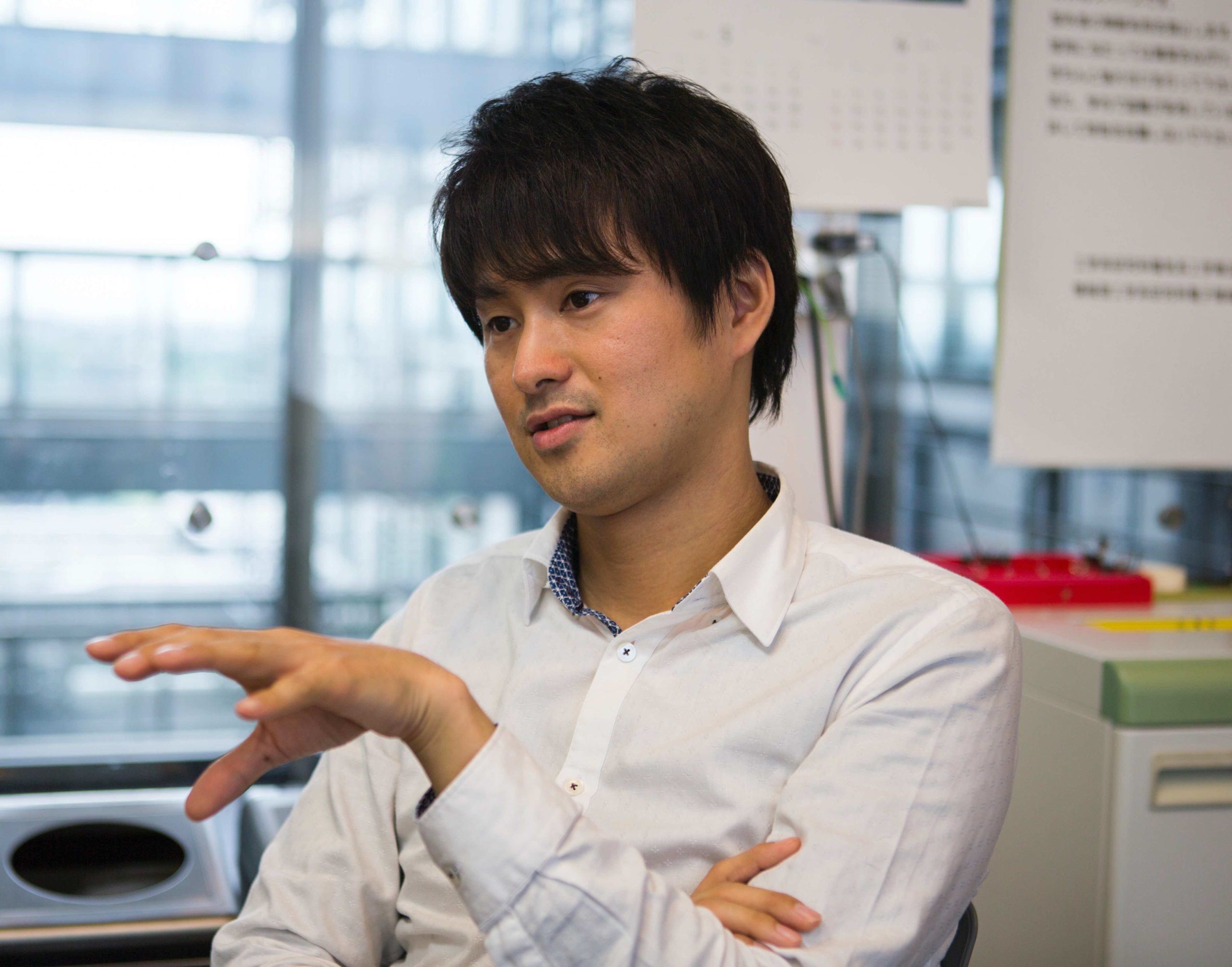
共同研究者:九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授
福嶋政期
-
研究・業務内容
・スマートラーニングデザインに関する研究
・VRとラーニングアナリティクスを組み合わせた学習支援システムのデザイン・開発研究
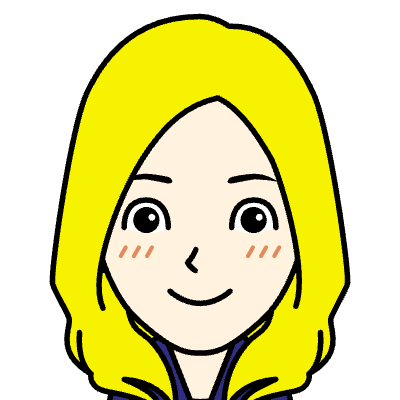
共同研究者:Research Professor Emerita at School of Information, University of Michigan
Stephanie D. Teasley
-
研究・業務内容
・メタ認知と学習行動との関係性におけるラーニングアナリティクス研究
学生・研究生等
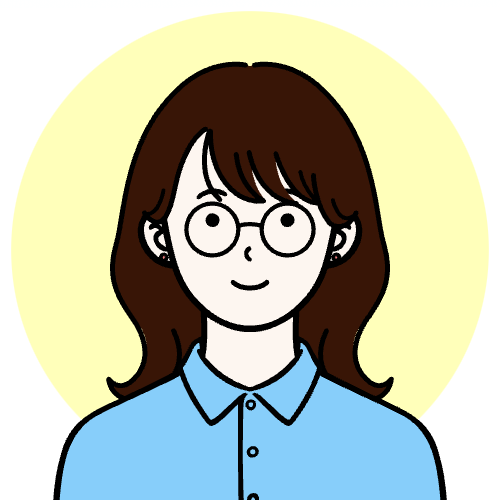
博士1年生
田中早代
出身校
- 修士:Faculty of Education, Monash University
- 学士: 広島大学 総合科学部
-
(1)研究・業務内容
学習者の自己調整学習を促進することを目的とした生成AI活用型英語ライティングフィードバックのデザイン・評価
-
(2)代表的な業績
・論文
Tanaka, S., & Saito, E. (2021). Examining the barriers experienced by EFL teachers when implementing technology in senior secondary schools in Japan: a self-study. PRACTICE, 3(2), 96–109. https://doi.org/10.1080/
25783858.2021.1968281

修士2年生
尾﨑康平
出身校
- 西南学院大学 法学部
-
(1)研究・業務内容
主体的なキャリア選択を促す探究型学習のデザインと評価
-
(2)代表的な業績
・発表等
尾﨑康平・耿学旺・山田政寛, 高校生のキャリア自己調整能力に関する分析, 日本教育工学会2025年春季全国大会
Ozaki,K., Geng, X., and Yamada, M., Exploring the Use of Learning Analytics to Support High School History Class: A Pilot Study, Proceedings of the 1st International Conference on Learning Evidence and Analytics (ICLEA 2025), 2025
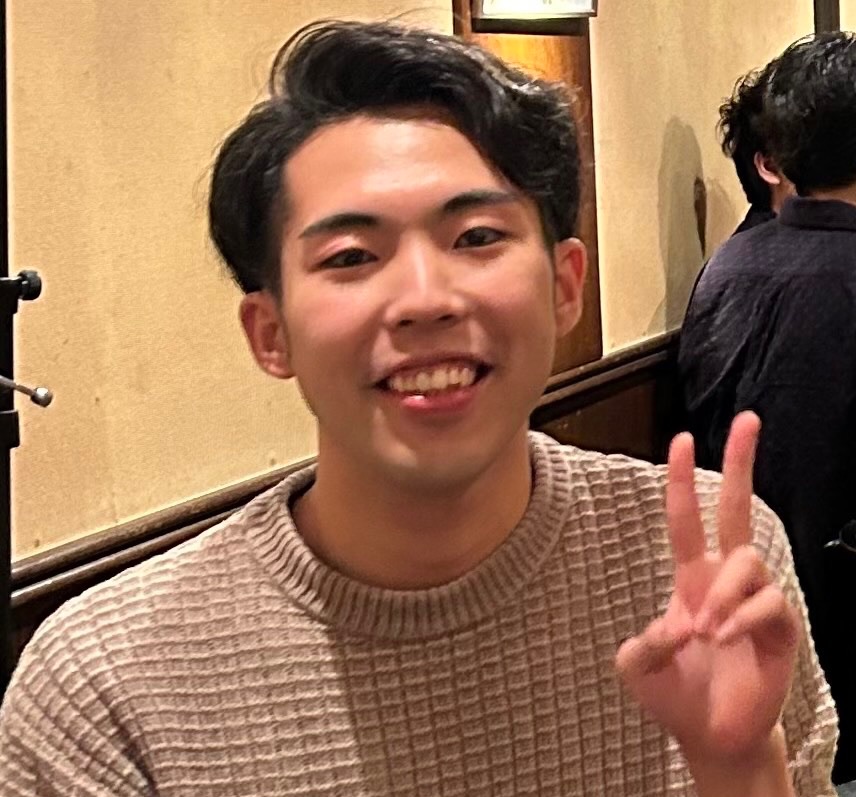
修士2年生
樋口尚宏
出身校
- 九州大学共創学部
-
(1)研究・業務内容
ラーニングアナリティクスを活用した学習フィードバックシステムの開発研究
-
(2)代表的な業績
・発表等
樋口尚宏・耿学旺・山田政寛(2024).授業改善を目的とした授業中におけるリアルタイムラーニングアナリティクスダッシュボードのデザイン,日本教育工学会2024年秋季全国大会
Higuchi, N., Geng, X., and Yamada, M., Designing a Teacher Inquiry System with Teaching and Learning Analytics Using Fine-Grained Data, Proceedings of the 1st International Conference on Learning Evidence and Analytics (ICLEA 2025), 2025
山田研究室で行っているゼミ活動の紹介
研究ゼミ
研究ゼミは2部構成になっています。第1部は学生・参加者が取り組んでいる研究や実践について発表を行い、その研究・実践を発展させるために議論を行うゼミになります。発表者が発表した研究や実践をよりよくするにはどうするべきか、どういうデータを取るべきか、どういうところで実践の場がありそうか、どういう評価方法をすべきか、いろいろ議論を行います。第2部は英語文献輪読です。教育工学の研究で必要になる基本的な理論を学ぶことを目的としています。現在はCambridge Handbook of Cognition and Educationを読んでいます。
開催頻度・時間:月2回程度(隔週) 火曜日17時00分〜19時30分(オンライン)
英語文献ゼミ
英語文献ゼミは、参加者の研究や実践に関係する英語論文を輪読するゼミです。教育工学の研究は国内だけではなく、国際的にも行われており、研究である以上、オリジナリティが高いことが求められます。オリジナリティが高い研究、実践をするには国内外の研究・実践論文にあたり、その論文の良い点・改善すべき点・限界点を検討する必要があります。このゼミでは、国際論文誌から読みたい論文を選んでもらい、読んで、3枚から5枚程度のレジュメにまとめてもらって、発表をしてもらいます。その後、発表者の研究における、その論文の位置づけ、今後の研究の展開など議論をし、研究方法を学びつつ、研究を発展させていくことを目的にしています。
開催頻度・時間:毎週月曜日 17時00分〜18時00分(オンライン)
統計ゼミ
統計ゼミは、教育工学研究を進めて行くに当たり、基本的な知識となる統計について学ぶゼミです。これは学生の自主ゼミとして進めています。私たちは統計学の研究をしているわけではないので、統計学を突き詰めていくことは目的としていません。ツールとして統計を使います。ですが、ツールとして使うにも、最低限の知識、ルールは理解しておかなくてはなりません。このゼミでは統計学に関する基礎的な文献を輪読したり、データ分析を実際に行いながら、ツールとしての統計を学んでいくことを目的としています。
開催頻度・時間:月1回・要問い合わせ
認知心理学ゼミ
認知心理学ゼミは、教育工学研究を進めて行くに当たり、基本的な理論の理解をするためのものです。これは学生の自主ゼミとして進めています。人は学習するにあたり、様々な情報を認知し、処理をし、自分なりの解釈をし、意味づけしていきます。その学習過程においては、様々な情報媒体から学ぶこともあれば、人間関係の中から徒弟的に学ぶなど、さまざまな状況の中で学習というものは発生します。しかし、その過程において、人間はどういう認知的処理を行うのでしょうか?それに関連する理論は数多くあり、教育工学研究を進めるに当たり、基礎的な理論となります。
開催頻度・時間:月1回・要問い合わせ
ゼミ参加のお問い合わせ
ゼミ参加の受付については、基本的にはWelcomeの姿勢ですが、「文献担当・発表担当はしたくないが、話を聞きたい」という受け身な方は受け入れていません。参加する以上、文献輪読の担当をして頂きますし、研究ゼミでは発表も担当して頂きます(目安として半年に1、2回程度)。また、責任を持って参加して頂きたいために、継続的に参加される方に限定して受け入れています(半年以上は参加してもらいたいです)。自分の研究だけではなく、他の参加者の研究も高めて、学んでいく強い意思を持つ、研究マインドあふれた方、Welcomeです。参加されたい方は、どのゼミに参加されたいのか、何のために参加したいのか、私にメールでご連絡ください。お待ちしております。